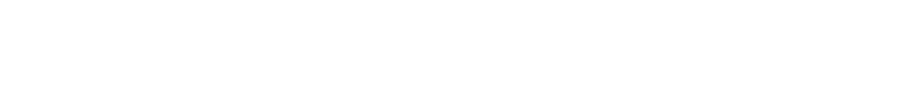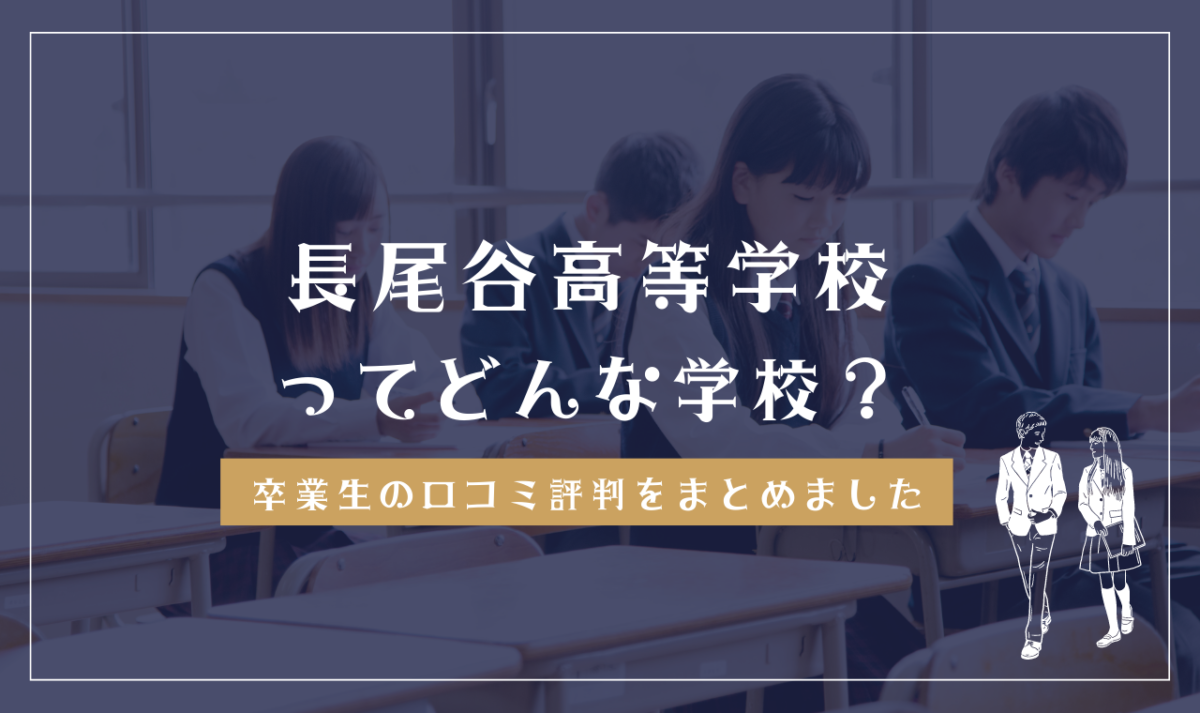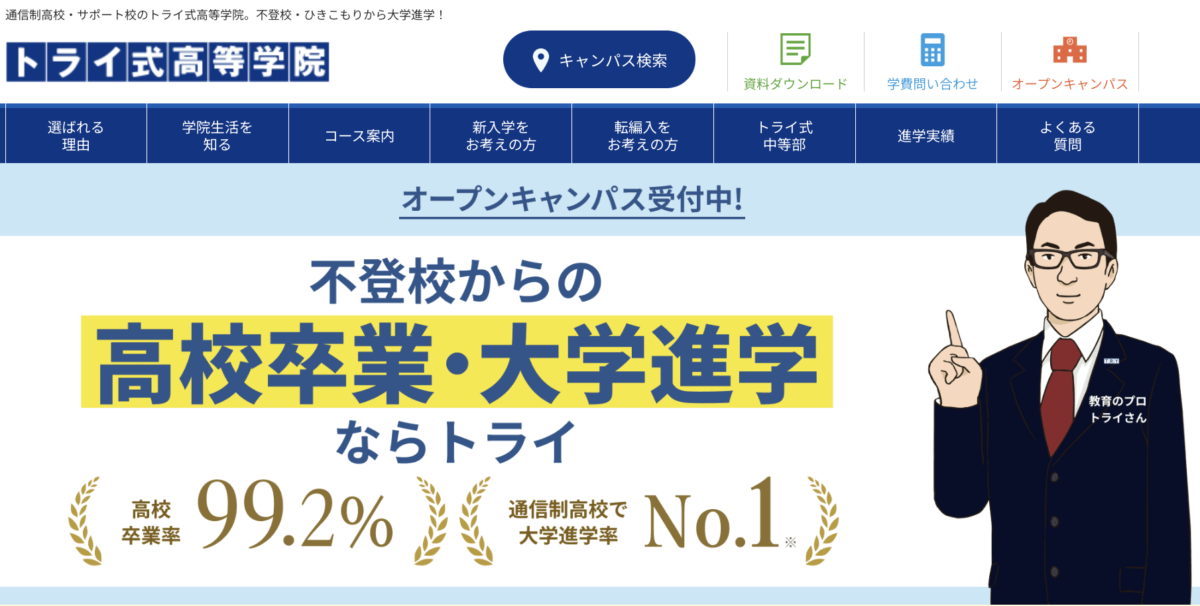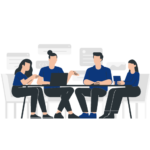長尾谷高等学校の学費
70,600円〜/年間
※上記は就学支援金適用時の金額
※住所を入力すると近くの人気校資料をまとめて請求できます
通信制高校の「長尾谷高等学校」ってどう?
学費や偏差値があるのか気になる・・・
 編集長 阪口
編集長 阪口
こんにちは、「通信制高校選びの教科書」編集長の阪口です。
長尾谷高等学校の学費は、
年間:70,600円〜
となっており、選択コースや登校頻度によって学費が変わります。。
入学にあたっては学力試験もないため、偏差値もありません。詳しい学費は募集要項や学校パンフレットを取り寄せて確認しましょう。
色んな通信制高校を調べているけど、色んな学校があって選べない!
3年通うところだし、学校選びで失敗したくないな・・・
 編集長 阪口
編集長 阪口
学校選びで失敗したくない場合は、近くにある通信制高校の資料がまとめて請求できるサイトを利用するのが便利です。
近所にどんな学校があるかわかりますし、オープンキャンパスや説明会情報も手に入ります。
家族で相談するときも、紙媒体の資料が手元にある方が話しやすいですよ。
長尾谷高等学校は1993年に開校した、大阪・京都・奈良にキャンパスを持つ広域の通信制高校です。
個人を尊重し、多彩な生徒に対応できる学習環境を作ることを念頭に、不登校や対人間関係のトラブル、病気などの問題を抱える生徒も積極的に受け入れてきました。
通信制としてはやや歴史の長い学校で、進学・就職共にノウハウがあります。加えて、個々の生徒が学びやすいよう、学習スケジュールには柔軟性があるのも魅力です。自身の目標に付かづくために、安心して努力できる場を探すなら、チェックしておきたい学校といえるでしょう。
この記事はAIによる自動生成ではなく、卒業生と通信制高校選びの専門家によって執筆・編集されています。

通信制高校は学費が安い学校が多いですが、だからといってサポートが全くない学校を選んでしまうと、勉強をひとりで進めることができずに退学になってしまうケースもあります。
・まずは人気校の情報を取り寄せる
・近所の通信制高校もみてみる
・比較しながら子どもと相談して決める
という流れで学校選びを進めていきましょう。
\入学してから後悔しない/
まずは人気校の情報を取り寄せる

| 学費 | 73,000円〜(詳細)
*通信コース/就学支援金適用時
*通学にかかる費用はキャンパスによって異なります |
| スクーリング | 年間5日間~ |
| 開講コース | ネットコース/通学コース/オンライン通学コース/通学プログラミングコース |
| 入学時期 | 4月、7月、10月、1月 ※転入生は随時受け付け |
| 専門授業 | 語学/プログラミング/特進コース(キャンパスによる) |
| 本校所在地 | 沖縄県うるま市与那城伊計 24(入学は全国から可) |
| キャンパス | 札幌、仙台、東京(御茶ノ水・秋葉原・代々木・渋谷・池袋・立川・町田)、横浜、大宮、千葉、柏、名古屋、浜松、岐阜、新潟、金沢、大阪(天王寺・梅田・心斎橋)、神戸、姫路、京都、広島、高松、福岡、北九州、鹿児島他 |
| 募集人数 | |
| 偏差値 | なし(偏差値詳細) |
| 出願期間 | 参考:2023年度募集日程
第1期:2022/9/30-2022/11/1
第2期:2022/11/4-2022/12/6
第3期:2022/12/9-2023/1/10
第4期:2023/1/13-2023/2/14
第5期:2023/2/17-2023/3/7
第6期:2023/3/10-2023/3/22
※転編入は随時募集 |
| 選抜方法 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
課題作文・面接
【ネットコース】
書類選考 |
| 検定料 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
15,000円
【ネットコース】
10,000円(事務手数料代込み) |
2023年度
| 国公立大 | 東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学、広島大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、岩手大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、茨城大学、千葉大学、電気通信大学、東京外国語大学、東京藝術大学、東京農工大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、山梨大学、信州大学、静岡大学、岐阜大学、島根大学、山口大学、香川大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学他 |
| 私立大学 | 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、成城大学、成蹊大学、明治学院大学、國學院大学、武蔵大学、南山大学、立命館アジア太平洋大学、津田塾大学、東京女子大学、昭和女子大学、共立女子大学、大妻女子大学、同志社女子大学、京都女子大学、武庫川女子大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、神戸女学院大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学、東京造形大学他 |
| 海外大学 | トロント大学、マンチェスター大学、キングス・カレッジ・ロンドン、シドニー大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、モナシュ大学マレーシア校、ウィスコンシン大学マディソン校、オークランド大学、トリニティ・カレッジ (ダブリン大学)、ニューカッスル大学他 |
N高等学校の2023年度合格実績
N高等学校・S高等学校ってどんな学校? N高やS高をはじめて知る方へ
https://www.youtube.com/watch?v=mxZbTaYk8N0&t=3sネットの高校の部活動!日本全国の部員と交流する『ネット部活』
N高等学校・S高等学校 大学合格実績速報発表会
こちらの学校はいじめ・不登校などの問題を抱えた方に対するケアがしっかりとしているとのことで編入しました。実際、特に問題なく、先生方をはじめ学校側がすごくそのあたりをケアしているのが感じられました。
しかし、メンタル的なサポートをしっかりとしてくれるのは有り難いことですが、そういうサポートを受けなければ学校生活を送れないというコンプレックスを感じてしまいました。そういう意味では少し我慢して普通の高校に通ってもよかったのかなと思います。
学校や先生の雰囲気は非常に素晴らしいです。もともと、人間関係などの問題を抱えているという前提で向き合ってくれますので、通学することにストレスは感じませんでした。
進路に関しては正直、最初は不安でしたが、アニメが好きな知り合いがたくさん増えました。同じ趣味を持つ友人ができたので、将来はアニメ関係の道を目指せたらと思います。
人間関係などの不安で将来が心配な方は安心して通われて大丈夫だと思います。何より、同じ境遇や立場な方が多いので、自分が孤立しているという不安は解消できると思います。
N高等学校は1年目の評価が高いですなぜなら他の学校とは違うこいうことを実感できたからです違いとは、パソコンのスキル、Adobeのスキル、タイピングのスピードなどは他の学生よりも1年間で圧倒的に伸びたと感じますまた自由時間が多く(自分のやりたいことに取り組める時間)資格取得などにも取り組むことができました。
2年生からは1年生の時と同じような感じなのでこの制度にあき、N高でできる様々な課外活動系を重点的に取り組みましたそのおかげで日本、世界など様々なことが知れました(課外活動は全国各地、海外の課外活動もあります)。また短期で語学留学に行き様々な成長をすることができました。また予備校にも通い始め学力も伸びすごく充実していました(ちなみに2年生は週3です)
3年生では受験のため課外活動とかは一切せずに勉強に集中しました私はn高の場合いかに自立できるかで、評価が1~5は変動してくると感じます理由は宿題がなかったり、学校の中で自習の時間が1日の半分を占めるからです。
その時間を自分のためになる時間として使うかはたまたYouTube見てしまうか生徒の判断ですが自習の時間を活かせるかでN高を検討した方が私は良いと感じました自分のやりたいことをすでに持っている人にとってN高はお勧めできる価値のある学校だと感じます
良かった点私は人間関係の悩みでN高等学校に変えたので、まず人付き合いを強制されないというところにとても安心感を感じられ良かったです。
次にN高等学校のネットコースはとても登校日数が少ないので往復3時間かけていた登校時間の短縮が出来たことや、どんな時間でも好きなだけ授業動画を見ることが出来る機能があり、自分の集中出来るタイミングや自分のその時にできる量をやる事が出来たため、自由な時間がとても増えました。
その時間を使い、自分のスキルアップの時間を多く取る事が出来たのは今でもとてもよかったと感じています。
悪かった点ネットコースなので先生や他の生徒達との繋がりが弱いです。The高校生のような青春を送るのは少し難易度が高いと感じます。一応N高等学校には部活のようなチャットグループがあるのですが、キャンパスで面識があるお友達同士しか喋っていないことが多いので、ネットコースの人は上手くいかないこともあるかもしれません。
学校について私が言ったらキャンパスの建物はとても綺麗で、机等も使いやすい形でした。自動販売機等もあり不便さを感じることは無かったです。コロナ対策もしっかりしていて安心して登校する事が可能です。
結論から申し上げると、この高校に通うことができて本当に良かったと思います。学習面に関しては、自己管理能力や自己学習能力が求められますが、その点に関しては他の通信制高校でも大差はないと思います。
N高等学校の一番素晴らしかった点は、プログラムやイベントの多さです。投資部や起業部などの他の学校にはないユニークな部活があったり、ニコニコ動画を活用した大久保な文化祭が執り行われたりするなど、この高校でしかできない体験をたくさんすることができました。また、進路サポートも充実していて、国内の大学や専門学校進学に関する指導だけではなく、海外大学への出願サポートもあるため、さまざまな進路希望に対応してくれます。先生方は比較的若く、穏やかな方々が多い印象です。
中には学生時代不登校だった先生もいらっしゃるので、学校に生きづらいという生徒に寄り添ってくれる先生もいらっしゃいます。費用に関しては、週五日の通学コースだと本当に高いです。おそらく、全日制の私立高校よりも高いと思います。学費を節約したい場合は、ネットコースにして、オンライン上でさまざまな部活やイベントに参加するのがいいのではないかと思います。
よかった点は全日制の高校いってた時よりかは時間に縛られずノーストレスで家で学習していたところや、他の高校生と違い時間がありふれていたので、すきな趣味に没頭したり、今まで習ってきてなかったスキルを習得する時間を作れたことがよかったところです。
悪かった点は、全日制とは違い自宅にいる時間が多く、それと授業も先生方から渡された動画や課題をこなすだけだったので人とのコミュニケーションのできる場がなくて友達を作ろうにも作れない状況でした、ですが年に三回は指定された場所で授業をうけるのがあり、同じ気持ちをもってる優しい方もいれば、口が悪い子もいたりで微妙でした。
学校の先生の雰囲気は、誰よりも優しく、誰よりも相談に乗れる方々がいて疲れた心を癒してくれる場所でもありました。全日制の高校の先生なんか大抵が心がないやつしかいないので通信は優しい方がいっぱいいました。最後に迷ってる子がいるとしたら、通信も悪くない場所です!
 編集長 阪口
編集長 阪口
・学費が安い(年間10万円程度)
・生徒数日本No.1(=生徒が最も選んでいる通信制高校)
・東大・国立難関私大の合格実績多数
と学費の安さ、実績、学びやすさは日本トップ。通信制高校進学を考えたら、最初に検討したい学校です。
N高等学校の資料を取り寄せる>>

| 学費 | 一人ひとりに合わせて最適な料金プランを作成。
詳細は公式サイトでお問い合わせください。 |
| 開講コース | 【普通科】高校卒業を目指すコース
【特進科】大学進学を目指すコース |
| 入学時期 | 新入学:4月 10月 / 編入転入:随時 |
| 専門授業 | 特進科(大学進学コース) |
| 本校所在地 | 東京都千代田区飯田橋 1-10-3 |
| キャンパス | 全国に120キャンパス以上 |
評価的には4かなと思います。でもそこまで悪いところがあるわけでもないのですが、普通の高校の方がいい気がします。
良かった点は、ネットコースなのであまり人と会わないことです。正直人とのコミュニケーションなどは得意ではない方だったのでその方がありがたかったです。なので周りを気にせずに自分自身で勉強に取り組むことができたのでよかったです。
悪かった点としては、これをいうのもあれなんですが人とのコミュニケーションが取れないこと、そうなることで今後の社会に出た時などに人とのコミュニケーションは必ずと言って必要なものなので困りました。なので今でもネットを使ったような仕事をしていて人とあまり関わらないような仕事をしているので結果よかったか悪かったかわかりません。
今後このような通信制の学校などを考えているのであれば私なりには正直、普通の高校に通っていろんな人とコミュニケーションを取ることが大事になってくるのかなと思いました
まず、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、通信制教育に特化した学校です。自分のペースで学習が進められるため、仕事やアルバイト、病気や怪我などで通学が難しい場合でも、学業を続けることができます。また、進路に合わせてカリキュラムが選べるため、自分の目標に向かって無理なく学ぶことができます。
次に、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、豊富な教材や学習支援が用意されています。学習教材は、オンラインで提供されるため、自宅や外出先など、好きな場所で学習ができます。また、学習相談や質問に対する返信など、サポート体制も充実しており、生徒が不安なく学習を進めることができます。
さらに、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、先進的な取り組みが特徴です。例えば、AIを活用した学習支援システムが導入されており、生徒の学習状況を分析し、適切なアドバイスを出すことで、効率的な学習を促進しています。また、単位制度を採用しているため、必要な単位を取得することができれば、自由に卒業時期を選択できるなど、柔軟な学習スタイルをサポートしています。
最後に地域に根ざした学校として、地域との交流やボランティア活動に力を入れていることも魅力的です。例えば、地域の祭りやイベントに参加したり、老人ホームや児童福祉施設などでボランティア活動を行ったりすることで、社会貢献の意識を育てることができます。
トライ式高等学院の東京キャンパスは生徒数も多く、部活動や修学旅行、留学制度もあり、全日制高校と変わらない学校生活を送ることができました。大学受験に特化した特進科は先生が受験などのプランを立ててくださり、分からないところは丁寧に教えてくれます。全日制高校にはない、復習する授業もあり無事に第一志望の国公立大学に進むことができました。
欠点としては学費がとても高いことです。提携通信制高校の学費に加えてサポート費用がかかるため、年間学費は100-120万円ほどでした。一般の全日制高校+予備校にかかる費用と考えると相応かなとは思いますが、入学を希望する方は学費の把握はしておくようにしましょう。
僕は高校2年生ときに、私立の全日制高校から転入しました。その際不登校だったため、1年生の取得単位数は0でした。ですが、留年をしたくなかった僕は、留年せずに大学に進学できる学校を探している際にこの高校を見つけました。学力テストはいつもギリギリだった上、授業もろくに行っていませんでしたが、トライ式高等学院はそんな僕でもマンツーマンで指導をしてくれ、無事に三年間で卒業することができました。この学校を選ばなければ大学には進学できなかったでしょう。
| 募集定員 | キャンパスにより異なる |
| 偏差値 | なし(詳細) |
| 出願期間 | 公式サイトにてご確認ください |
| 選抜方法 | 面接+作文(一般入試のみ) |
| 進路内訳 | 卒業率:99.5%
*2022年3月卒業生の実績
大学進学率:69.7%
※大学進学率とは、進路決定者のうちの大学・短大・専門職大学に合格した者において。卒業/大学進学率2024年自社調べ。出典:文部科学省「学校基本調査」在籍生徒数3500人以上の通信制高校・サポート校において進学率全国1位。2023/3/23 産経メディックス調べ。令和4年度の学校基本調査:大学進学率23% |
| 国公立大学 | 東京大学/大阪大学/北海道大学/九州大学/神戸大学/筑波大学/金沢大学/広島大学/熊本大学/北海道教育大学/山形大学/東京学芸大学/電気通信大学/新潟大学/信州大学/静岡大学/福井大学/京都教育大学/京都工芸繊維大学/山口大学/愛媛大学/高知大学/長崎大学/鹿児島大学/琉球大学/前橋工科大学/東京都立大学/横浜市立大学/諏訪東京理科大学/愛知県立大学/神戸市外国語大学/兵庫県立大学/広島市立大学/北九州市立大学/熊本県立大学 ※2024年度大学入試の実績 |
| 私立大学 | 早稲田大学/慶應義塾大学/上智大学/東京理科大学/学習院大学/明治大学/青山学院大学/立教大学/中央大学/法政大学/関西学院大学/関西大学/同志社大学/立命館大学/日本大学/東洋大学/駒澤大学/専修大学/成城大学/成蹊大学/津田塾大学/南山大学/京都産業大学/近畿大学/甲南大学/龍谷大学/西南学院大学 ※2024年度大学入試の実績 |
 編集長 阪口
編集長 阪口
マンツーマンで指導が基本で、どんな状況の生徒でも柔軟に対応してもらえます。不登校や発達障害を持つ生徒、大学進学を考えている生徒に特におすすめです。
トライ式高等学院の資料を取り寄せる>>
目次
長尾谷高等学校はどんな学校? 特徴を解説

| 学費 | 70,600円〜(詳細)
*通信コース/就学支援金適用時
*通学にかかる費用はキャンパスによって異なります |
| スクーリング | 授業日の内、自分が選択した科目の授業に出席する |
| 開講コース | ベーシックコース、海外語学スクーリング、進学クラスなど |
| 入学時期 | 新入学:4月 10月 / 編入転入:随時 |
| 専門授業 | 基礎科目、語学研修、 異文化理解、タイリング入門など |
| 本校所在地 | 枚方市長尾元町2-29-27 |
| キャンパス | 枚方市長尾元町2-29-27(枚方本校)
大阪市北区中津6-5-17(梅田校)
大阪市浪速区元町1-11-1(なんば校) |
良かった点は簿記やマーケティングなどを学べた、アルバイトなど学業以外のことにも努力がしやすい
、授業以外の特別活動の選択肢が豊富、などです。
一方、悪かった点はコースなしのため友達ができにくい、うざい教師がいたことです。
卒業後の進路は軽い面談がある程度で自分から行動しない限りは親身になってくれません。良くも悪くも主体性が必要となる学校だと思います。
学校の雰囲気は普通の高校と同じで、気軽に先生に声をかけたりかけられたりと明るい雰囲気です。しかし、一回だけ教員同士が言い合いのような喧嘩をしていました。その時は少し不快な気分になりました。
もう一つ気になる点は、私が在籍しているときに赴任してきた体育教師が厳しく通信制の高校には合わない先生だと思いました。
通信制高校ではコミュニュケーションがうまく取れない生徒が多くいる中、昭和の体育教師が赴任してきたのは不思議に思いました。その他、面白くないイジりを教員にされたことがすごく不快で今でも思い出すとイライラします。
私は、もともと全日制に通っていました。しかし、自称進学校で、毎日勉強に追われて嫌気がさして、不登校になりました。
出席日数も足りなくなってきて、どうしようかと思ったとき、通信制高校の存在を知りました。
私が通っていた通信制高校の特徴は二つあります。
一つは夏休みや春休みがとにかく長いです。自由な時間が多いのでその間はアルバイトや趣味に使っていました。
二つ目は、各教科の単位取得に必要な出席日数も少ないことです。学校嫌いの私でも、難なく通うことができました。
私はなるべく早くスクーリングを終わらせたかったので、学期の前半は頑張って出席して、後半は学校にいかなくてもいいようにしてました。
これは私の例えすが、自分のライフスタイルに合わせて通うことができます。
考えられる懸念は、やはり交友関係が浅くなってしまうのではないかという点でしょうか。
私の高校では、特活と呼ばれる学校行事に参加できるので、そこで友達を作っている人もいました。でも私は友達を作ることに抵抗があったので、ドライな雰囲気も嫌いじゃなかったです。
私が通っていた高校は月に1回しか登校しなくてよくて本当に楽でした。残りの時間は自宅学習で宿題をやるというスタイルだったので一人でじっくりと考えながらゆっくりと学習することができ知識が血肉となったように思います。
先生も月に数回しか授業せず残りの時間はほとんど地域活動に参加してボランティアの掃除などをするという具合でしたのでゆったりとしており良かったと思います。質問にも気軽に応じてくれ学習もはかどりました。
来ている生徒には芸能人などもいて仲良くなれたりして良かったです。やはり月1回しか登校しないので時間の都合がつくというのが通信制高校最大のウリだと思います。
仕事しながら通っている人がほとんどでしたので学校は暇でもみんな忙しく生きていたようです。卒業後の進路は様々で大学に進む人や会社に勤める人、さらには芸能活動を続ける人や相撲部屋に進む人などいろんな人がいました。通信制なのでやはり変わった人が多かったように思います。
長尾谷高校は決まった授業時間を受け、レポートを提出。テストを受け、半年に1回繰り越しで1年間必要な単位を取得していく形です。金額は私立と同じぐらいと思います。メリットとしましては、服装・髪型の自由。年代も10代の子から50代の方がおられました。学校も1限だけ行って後はバイトに行けたり、この日にまとめて授業を受けようとか時間割を見ながら決めれるので融通がきくと思います。
デメリットは、学費が高いことと学割がきかない事です。生徒手帳はあるんですけど、電車の定期とかは毎日では無いので買えないです。体育の単位とるのも勉強とは違う場所の地域の公民館とかに行くので少し大変でした。ですが、遠足 校外学習 スキー宿泊とかもあり本人希望で行けるので思い出も作れて、個性も大切にしてくれるので楽しいです。先生も相談に乗ってくれて、私は1年休学して卒業までに4年かかりましたが、人間関係のトラブル等も無く、友達も出来て通信を選択して良かったなと考えています。
| 偏差値 | なし(詳細) |
| 出願期間 | 一次:2023年1月20日~2月9日
二次:2023年2月13日~3月2日
三次:2023年3月8日~3月23日 |
| 選抜方法 | 一次:書類審査+面接+学科試験
一次以降:書類審査+面接+作文
転入生:書類審査+面接 |
| 検定料 | 10,000円 |
| 主な合格実績 | 広島大、岡山大、愛媛大、京都薬科大、京都女子大、同志社女子大、東京農業大、立命館大、関西学院大、関西大、京都産業大、近畿大、龍谷大、関西外国語大、甲南大、甲南女子大、甲南大、神戸学院大、神戸国際大、神戸女子大、追手門学院大、藍野大、大阪大谷大、大阪学院大、大阪経済大、大阪経済法科大、大阪芸術大、大阪工業大、大阪国際大、大阪産業大、大阪商業大、大阪電気通信大、大阪人間科学大、大谷大、大手前大、韓国外国語大、関西国際大、京都外国語大、京都芸術大 など |
長尾谷高等学校 学校紹介
通信制高校ってどんなところ?
進学に強く名門大学への合格者が多数
通信制高校の中でも、大学進学へに力を入れているのが長尾谷高等学校の特徴です。
本格的な進学対策クラスも用意されており、国公立、名門私大に挑戦できます。合格実績は多数で、トップクラスの難易度を誇る学校にも生徒を送り出してきました。
進学校や塾での指導経験者が在籍しているなど、大学受験のバックアップ体制が整っています。不登校などで思うように勉強できなかったけれど、目標の大学にチャレンジしたい方はリサーチしておきたい学校です。
部活動や学校行事で素敵な思い出を作れる
通信制高校の中では、クラブ活動が活発な学校です。野球やバスケ、剣道などの運動部はもちろん、音楽や写真などの文化部も充実しています。
しかも取り組みは熱心で、全国大会に出場した部も見当たりました。
本格的にクラブ活動を検討できるので、これまでスポーツ経験がある方や、やりがいを見つけたい場合にも適しています。加えて、校外学習や修学旅行などの学校行事も多数用意されているのが魅力。素敵な思い出を作れるでしょう。
柔軟性が高い
服装は自由ながら指定の制服もあり、好きな方を選べます。また、スクーリングも難しい時は、救済措置が用意されているのも魅力。守るべきルールもありますが、柔軟性も併せ持った学校です。
 編集長 阪口
編集長 阪口
学校選びで失敗したくない場合は、近くにある通信制高校の資料がまとめて請求できるサイトを利用するのが便利です。
近所にどんな学校があるかわかりますし、オープンキャンパスや説明会情報も手に入ります。
家族で相談するときも、紙媒体の資料が手元にある方が話しやすいですよ。
長尾谷高等学校の学費は高い?
| 入学金 | 70,000円 |
|---|
| 授業料 | 300,000円(25単位取得の場合/就学支援金の対象で最大無料) |
|---|
| 諸活動費 | 600円 |
|---|
| 卒業経費 | 8000円(3年次のみ) |
|---|
| 同窓会費 | 3000円(3年次のみ) |
|---|
| 教材費・実習費 | 実費 |
|---|
| サポート費用 | 進学に特化したコースやクラスを希望する場合は、その他費用がかかります |
|---|
| 初年度合計 | 70,600円〜370,600円 |
|---|
私立の通信制高校としてはリーズナブル
25単位の履修で、基本となる学費はおよど26万。私立の通信制高校で考えると費用はリーズナブルと言えるでしょう。
私立では20万円~100万円を超えるケースがありますが、一般的には30万円~50万円程度になる学校が良く見当たります。結論としては、他に安い学校はあるものの、進学と就職に強くて、何かとメリットが多いのが特徴ですから、費用対効果に優れていると言えそうです。
追加費用には注意
選んだコースやカリキュラムによっては、追加の費用が生じる可能性はあります。これは他の学校でも同じですが、標準のカリキュラムに色々と追加すると、学費は高くなってくるので気を付けて下さい。
もちろん、高校での勉強は将来への大切な投資ですから、安ければ良いと言うわけではありません。やりたいことや必要なことを見極めて、無駄や無理のないよう工夫したいものです。
奨学金や就学支援金制度を活用する
国や地方自治体などが奨学金・支援金の制度を用意しているので、活用を検討してみましょう。学費を抑えたり、支払い負担を軽減したりできます。具体的には育英会や、大阪の授業料軽減措置などが利用可能です。詳しくは、長尾谷高等学校に相談窓口が設けられているので、問い合わせてみましょう。
ファミリー特典を利用しよう
ご両親もしくは兄弟姉妹が長尾谷高等学校を卒業しているか、在学中の場合には学費の一部が免除される特典があります。家族が通ったのなら費用も安くなりますし、学校のリアルな体験談もきけるので大いに参考になるはずです。
最初に検討したいおすすめ通信制高校【TOP3】
長尾谷高等学校に偏差値はある?

長尾谷高等学校には偏差値というものがありません。
長尾谷高等学校に偏差値がないのは、通信制の高校であることが主な理由です。
全日制課程の高校には、偏差値という概念が設定されていますが、通信制高校には偏差値という概念自体がないために、偏差値を決められないようになっています。
長尾谷高等学校に偏差値がないもう一つの理由は、この学校の入学試験の内容です。偏差値を調べるために必要なのは、国語や数学など各教科のテストの成績ですが、長尾谷高等学校では全ての受験生に学力試験を課していないため、偏差値を計算することができません。
偏差値がなくても、勉強しやすい長尾谷高等学校
長尾谷高等学校には偏差値はありませんが、生徒にとって勉強しやすい環境が整っている学校です。
この学校の勉強しやすい理由の一つが、関西の各地に校舎があることです。本校がある枚方をはじめ、大阪府には全部で3つの校舎があります。大阪府以外の場所にも校舎はあり、京都府の校舎は京都市の中京区にあります。奈良県の校舎があるのは、奈良市の大宮町です。
選べるクラスの種類が多いことも、この学校が勉強しやすいポイントで、週に3回スクーリングができるのは、標準カリキュラムのコースです。通学する回数を多めにしたい人に向いています。自宅学習を中心にしたサタデーコースもあり、スクーリングは所定の土曜日だけです。
長尾谷高等学校の入試情報・対策

長尾谷高等学校は普通科を募集し、年間400人ほどの生徒を受け入れています。学校は前期と後期の2回、入学試験を実施しています。前期の出願期間は1月から3月までの期間で、一次から三次まで3回に分かれています。
一次出願は1月後半から2月前半、二次出願は2月後半から3月前半に行われます。三次出願は3月前半から後半にかけて受け付けています。
後期の出願期間は、9月前半から後半にかけてで、複数回に分かれていません。
出願は、受験者が直接入学を希望する校舎に提出する必要があります。平日の受付時間は午前9時から午後4時までで、土曜日は午前9時から午後2時までの受付時間となっています。なお、日曜日や祝日は受付していません。
長尾谷高等学校の入試対策
長尾谷高等学校の入試内容は受験日程によって異なります。
前期入学の一次試験では、国語と数学の学科試験と面接、書類審査があります。二次・三次試験では、学科試験はなく、課題作文、面接、書類審査が行われます。
後期入学試験も課題作文、面接、書類審査がありますが、学科試験はありません。
試験結果は、試験日から3日以内に郵送で通知されます。
長尾谷高等学校に合格するためには、学科試験がある前期一次試験に備えて、しっかりと勉強することが重要です。面接に備えるためには、面接の予行練習や、質問されそうな質問に回答を用意することが有効です。
また、前期二次・三次試験や後期試験を受験する受験生には、課題作文に対する対策も必要です。課題に沿った文章を書く練習をすることが重要です。
最初に検討したいおすすめ通信制高校【TOP3】
長尾谷高等学校のコース/カリキュラムについて

長尾谷高等学校は枚方本校、梅田校、なんば校、京都校、奈良校の5つのキャンパスがあり、キャンパスによって開設されているコースは異なります。こちらでは共通している3つのコースを主に紹介します。
- 週3日のスクーリングで卒業可能な「標準カリキュラム」
- 中学新卒生対象のクラス制「スタートクラス」
- 語学と高校卒業を同時に目指す「海外語学スクーリング」
「標準カリキュラム」で高卒資格を習得可能
多数のコースや選択科目が用意されていますが、長尾谷高等学校では標準カリキュラムを履修すれば高卒資格が取得できるようになっています。
卒業に必要な科目さえ履修すれば、残りは用意されている科目の中から好きなものを自由に選び通いやすい日に出席すればOK。普通科の学習範囲もしっかりと学びつつ、他にも色々な楽しい科目に挑戦できるのが魅力です。
科目は美容関係やクッキング、歴史、散策などの特別なものがたくさん用意されています。これらのユニークな科目を通して、自身の目標や夢が見つかる可能性もあるでしょう。もちろん、勉強の息抜きにもなります。
大学受験対策プログラム
梅田校と京都校は、一流大学へも多数の生徒を送り出してきた、本格的な進学サポートプログラムが用意されています。
通常の科目では単位をとることに専念し、受験対策プログラムは進学希望者が集中して取り組めるような環境を整備しています。
通信制ならではの持ち味を生かして学習を進めますので、スケージュールにも無理がありません。更に少人数制で、全生徒に満遍なく指導が行き届くよう、気を配っています。
「スタートクラス」
スタートクラスは生徒が通信制に慣れるためのクラスで、慣れるまでの間クラス担当員が生徒を手厚くサポートが入ります。
中学からのギャップ対策で中学の全日制に似たシステムから始まります。全日制の中学から通信制高校は生活の変化が大きいので、慣れるまでサポートしてくれるのは一考の価値があります。
「海外語学スクーリング」
グローバル化に対応できるよう、海外留学をサポートしているのは特筆点です。ネイティブな英会話を学べる機会を設けており、留学も選択肢になります。また、留学までいかなくても、海外実習に参加することも可能です。
最初に検討したいおすすめ通信制高校【TOP3】
長尾谷高等学校のサポート体制ってどう?

長尾谷高等学校は、開校以来、不登校や対人トラブルなど、多様な問題を抱える生徒を支援してきた実績があるため、充実したサポート体制が期待できます。
学校にカウンセラーが常駐していることは記載されていませんが、不登校や自宅から出ることが難しい生徒に向けた配慮がいたるところに見られます。また、信頼できる教師に相談しやすいチューター制度があることや、学校に行かずに学習できるオンライン学習プラットフォームやツールが多数用意されていることも特徴です。
例えば、レポート提出が容易になっていたり、サイバーキャンパスを利用して様々な学習ができたりするなどの工夫があります。さらに、校舎によっては、自宅学習を中心としたコースを選択することで、登校日数を少なくできる場合もあります。心療内科への通院中や、週3日の登校が困難な生徒など、健康状態に関係なく、多様な生徒を受け入れています。
長尾谷高等学校のメリット(向いている人)

進学・就職共に強みがあるので、卒業後の進路については選択肢が広がります。難関大学に挑戦するのも良いですし、有名企業への就職も不可能ではありません。また、グループの専門学校にも進めます。
今後は更に必要性が高まると考えられているのが、英会話や国際社会への理解です。この学校では留学や現地実習などを通して、本格的に国際交流に取り組めるのがメリットと言えます。
長尾谷高等学校のデメリット(向いていない人)
大阪・京都・奈良に学校はありますが、校舎の数が限られています。原則、週に3日のスクーリングがあるため、通学圏内にキャンパスがあるかは必ず確認するようにしましょう。
他には年間数日の学校もあるため、スクーリングを極力減らしたい方にはデメリットと言えます。学校自体が気に入っている場合は、サタデーコースなら原則、週一回で済むので検討してみてはいかがでしょう。
 編集長 阪口
編集長 阪口
学校選びで失敗したくない場合は、近くにある通信制高校の資料がまとめて請求できるサイトを利用するのが便利です。
近所にどんな学校があるかわかりますし、オープンキャンパスや説明会情報も手に入ります。
家族で相談するときも、紙媒体の資料が手元にある方が話しやすいですよ。

通信制高校は学費が安い学校が多いですが、だからといってサポートが全くない学校を選んでしまうと、勉強をひとりで進めることができずに退学になってしまうケースもあります。
・まずは人気校の情報を取り寄せる
・近所の通信制高校もみてみる
・比較しながら子どもと相談して決める
という流れで学校選びを進めていきましょう。
\入学してから後悔しない/
まずは人気校の情報を取り寄せる

| 学費 | 73,000円〜(詳細)
*通信コース/就学支援金適用時
*通学にかかる費用はキャンパスによって異なります |
| スクーリング | 年間5日間~ |
| 開講コース | ネットコース/通学コース/オンライン通学コース/通学プログラミングコース |
| 入学時期 | 4月、7月、10月、1月 ※転入生は随時受け付け |
| 専門授業 | 語学/プログラミング/特進コース(キャンパスによる) |
| 本校所在地 | 沖縄県うるま市与那城伊計 24(入学は全国から可) |
| キャンパス | 札幌、仙台、東京(御茶ノ水・秋葉原・代々木・渋谷・池袋・立川・町田)、横浜、大宮、千葉、柏、名古屋、浜松、岐阜、新潟、金沢、大阪(天王寺・梅田・心斎橋)、神戸、姫路、京都、広島、高松、福岡、北九州、鹿児島他 |
| 募集人数 | |
| 偏差値 | なし(偏差値詳細) |
| 出願期間 | 参考:2023年度募集日程
第1期:2022/9/30-2022/11/1
第2期:2022/11/4-2022/12/6
第3期:2022/12/9-2023/1/10
第4期:2023/1/13-2023/2/14
第5期:2023/2/17-2023/3/7
第6期:2023/3/10-2023/3/22
※転編入は随時募集 |
| 選抜方法 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
課題作文・面接
【ネットコース】
書類選考 |
| 検定料 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
15,000円
【ネットコース】
10,000円(事務手数料代込み) |
2023年度
| 国公立大 | 東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学、広島大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、岩手大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、茨城大学、千葉大学、電気通信大学、東京外国語大学、東京藝術大学、東京農工大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、山梨大学、信州大学、静岡大学、岐阜大学、島根大学、山口大学、香川大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学他 |
| 私立大学 | 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、成城大学、成蹊大学、明治学院大学、國學院大学、武蔵大学、南山大学、立命館アジア太平洋大学、津田塾大学、東京女子大学、昭和女子大学、共立女子大学、大妻女子大学、同志社女子大学、京都女子大学、武庫川女子大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、神戸女学院大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学、東京造形大学他 |
| 海外大学 | トロント大学、マンチェスター大学、キングス・カレッジ・ロンドン、シドニー大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、モナシュ大学マレーシア校、ウィスコンシン大学マディソン校、オークランド大学、トリニティ・カレッジ (ダブリン大学)、ニューカッスル大学他 |
N高等学校の2023年度合格実績
N高等学校・S高等学校ってどんな学校? N高やS高をはじめて知る方へ
https://www.youtube.com/watch?v=mxZbTaYk8N0&t=3sネットの高校の部活動!日本全国の部員と交流する『ネット部活』
N高等学校・S高等学校 大学合格実績速報発表会
こちらの学校はいじめ・不登校などの問題を抱えた方に対するケアがしっかりとしているとのことで編入しました。実際、特に問題なく、先生方をはじめ学校側がすごくそのあたりをケアしているのが感じられました。
しかし、メンタル的なサポートをしっかりとしてくれるのは有り難いことですが、そういうサポートを受けなければ学校生活を送れないというコンプレックスを感じてしまいました。そういう意味では少し我慢して普通の高校に通ってもよかったのかなと思います。
学校や先生の雰囲気は非常に素晴らしいです。もともと、人間関係などの問題を抱えているという前提で向き合ってくれますので、通学することにストレスは感じませんでした。
進路に関しては正直、最初は不安でしたが、アニメが好きな知り合いがたくさん増えました。同じ趣味を持つ友人ができたので、将来はアニメ関係の道を目指せたらと思います。
人間関係などの不安で将来が心配な方は安心して通われて大丈夫だと思います。何より、同じ境遇や立場な方が多いので、自分が孤立しているという不安は解消できると思います。
N高等学校は1年目の評価が高いですなぜなら他の学校とは違うこいうことを実感できたからです違いとは、パソコンのスキル、Adobeのスキル、タイピングのスピードなどは他の学生よりも1年間で圧倒的に伸びたと感じますまた自由時間が多く(自分のやりたいことに取り組める時間)資格取得などにも取り組むことができました。
2年生からは1年生の時と同じような感じなのでこの制度にあき、N高でできる様々な課外活動系を重点的に取り組みましたそのおかげで日本、世界など様々なことが知れました(課外活動は全国各地、海外の課外活動もあります)。また短期で語学留学に行き様々な成長をすることができました。また予備校にも通い始め学力も伸びすごく充実していました(ちなみに2年生は週3です)
3年生では受験のため課外活動とかは一切せずに勉強に集中しました私はn高の場合いかに自立できるかで、評価が1~5は変動してくると感じます理由は宿題がなかったり、学校の中で自習の時間が1日の半分を占めるからです。
その時間を自分のためになる時間として使うかはたまたYouTube見てしまうか生徒の判断ですが自習の時間を活かせるかでN高を検討した方が私は良いと感じました自分のやりたいことをすでに持っている人にとってN高はお勧めできる価値のある学校だと感じます
良かった点私は人間関係の悩みでN高等学校に変えたので、まず人付き合いを強制されないというところにとても安心感を感じられ良かったです。
次にN高等学校のネットコースはとても登校日数が少ないので往復3時間かけていた登校時間の短縮が出来たことや、どんな時間でも好きなだけ授業動画を見ることが出来る機能があり、自分の集中出来るタイミングや自分のその時にできる量をやる事が出来たため、自由な時間がとても増えました。
その時間を使い、自分のスキルアップの時間を多く取る事が出来たのは今でもとてもよかったと感じています。
悪かった点ネットコースなので先生や他の生徒達との繋がりが弱いです。The高校生のような青春を送るのは少し難易度が高いと感じます。一応N高等学校には部活のようなチャットグループがあるのですが、キャンパスで面識があるお友達同士しか喋っていないことが多いので、ネットコースの人は上手くいかないこともあるかもしれません。
学校について私が言ったらキャンパスの建物はとても綺麗で、机等も使いやすい形でした。自動販売機等もあり不便さを感じることは無かったです。コロナ対策もしっかりしていて安心して登校する事が可能です。
結論から申し上げると、この高校に通うことができて本当に良かったと思います。学習面に関しては、自己管理能力や自己学習能力が求められますが、その点に関しては他の通信制高校でも大差はないと思います。
N高等学校の一番素晴らしかった点は、プログラムやイベントの多さです。投資部や起業部などの他の学校にはないユニークな部活があったり、ニコニコ動画を活用した大久保な文化祭が執り行われたりするなど、この高校でしかできない体験をたくさんすることができました。また、進路サポートも充実していて、国内の大学や専門学校進学に関する指導だけではなく、海外大学への出願サポートもあるため、さまざまな進路希望に対応してくれます。先生方は比較的若く、穏やかな方々が多い印象です。
中には学生時代不登校だった先生もいらっしゃるので、学校に生きづらいという生徒に寄り添ってくれる先生もいらっしゃいます。費用に関しては、週五日の通学コースだと本当に高いです。おそらく、全日制の私立高校よりも高いと思います。学費を節約したい場合は、ネットコースにして、オンライン上でさまざまな部活やイベントに参加するのがいいのではないかと思います。
よかった点は全日制の高校いってた時よりかは時間に縛られずノーストレスで家で学習していたところや、他の高校生と違い時間がありふれていたので、すきな趣味に没頭したり、今まで習ってきてなかったスキルを習得する時間を作れたことがよかったところです。
悪かった点は、全日制とは違い自宅にいる時間が多く、それと授業も先生方から渡された動画や課題をこなすだけだったので人とのコミュニケーションのできる場がなくて友達を作ろうにも作れない状況でした、ですが年に三回は指定された場所で授業をうけるのがあり、同じ気持ちをもってる優しい方もいれば、口が悪い子もいたりで微妙でした。
学校の先生の雰囲気は、誰よりも優しく、誰よりも相談に乗れる方々がいて疲れた心を癒してくれる場所でもありました。全日制の高校の先生なんか大抵が心がないやつしかいないので通信は優しい方がいっぱいいました。最後に迷ってる子がいるとしたら、通信も悪くない場所です!
 編集長 阪口
編集長 阪口
・学費が安い(年間10万円程度)
・生徒数日本No.1(=生徒が最も選んでいる通信制高校)
・東大・国立難関私大の合格実績多数
と学費の安さ、実績、学びやすさは日本トップ。通信制高校進学を考えたら、最初に検討したい学校です。
N高等学校の資料を取り寄せる>>

| 学費 | 一人ひとりに合わせて最適な料金プランを作成。
詳細は公式サイトでお問い合わせください。 |
| 開講コース | 【普通科】高校卒業を目指すコース
【特進科】大学進学を目指すコース |
| 入学時期 | 新入学:4月 10月 / 編入転入:随時 |
| 専門授業 | 特進科(大学進学コース) |
| 本校所在地 | 東京都千代田区飯田橋 1-10-3 |
| キャンパス | 全国に120キャンパス以上 |
評価的には4かなと思います。でもそこまで悪いところがあるわけでもないのですが、普通の高校の方がいい気がします。
良かった点は、ネットコースなのであまり人と会わないことです。正直人とのコミュニケーションなどは得意ではない方だったのでその方がありがたかったです。なので周りを気にせずに自分自身で勉強に取り組むことができたのでよかったです。
悪かった点としては、これをいうのもあれなんですが人とのコミュニケーションが取れないこと、そうなることで今後の社会に出た時などに人とのコミュニケーションは必ずと言って必要なものなので困りました。なので今でもネットを使ったような仕事をしていて人とあまり関わらないような仕事をしているので結果よかったか悪かったかわかりません。
今後このような通信制の学校などを考えているのであれば私なりには正直、普通の高校に通っていろんな人とコミュニケーションを取ることが大事になってくるのかなと思いました
まず、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、通信制教育に特化した学校です。自分のペースで学習が進められるため、仕事やアルバイト、病気や怪我などで通学が難しい場合でも、学業を続けることができます。また、進路に合わせてカリキュラムが選べるため、自分の目標に向かって無理なく学ぶことができます。
次に、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、豊富な教材や学習支援が用意されています。学習教材は、オンラインで提供されるため、自宅や外出先など、好きな場所で学習ができます。また、学習相談や質問に対する返信など、サポート体制も充実しており、生徒が不安なく学習を進めることができます。
さらに、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、先進的な取り組みが特徴です。例えば、AIを活用した学習支援システムが導入されており、生徒の学習状況を分析し、適切なアドバイスを出すことで、効率的な学習を促進しています。また、単位制度を採用しているため、必要な単位を取得することができれば、自由に卒業時期を選択できるなど、柔軟な学習スタイルをサポートしています。
最後に地域に根ざした学校として、地域との交流やボランティア活動に力を入れていることも魅力的です。例えば、地域の祭りやイベントに参加したり、老人ホームや児童福祉施設などでボランティア活動を行ったりすることで、社会貢献の意識を育てることができます。
トライ式高等学院の東京キャンパスは生徒数も多く、部活動や修学旅行、留学制度もあり、全日制高校と変わらない学校生活を送ることができました。大学受験に特化した特進科は先生が受験などのプランを立ててくださり、分からないところは丁寧に教えてくれます。全日制高校にはない、復習する授業もあり無事に第一志望の国公立大学に進むことができました。
欠点としては学費がとても高いことです。提携通信制高校の学費に加えてサポート費用がかかるため、年間学費は100-120万円ほどでした。一般の全日制高校+予備校にかかる費用と考えると相応かなとは思いますが、入学を希望する方は学費の把握はしておくようにしましょう。
僕は高校2年生ときに、私立の全日制高校から転入しました。その際不登校だったため、1年生の取得単位数は0でした。ですが、留年をしたくなかった僕は、留年せずに大学に進学できる学校を探している際にこの高校を見つけました。学力テストはいつもギリギリだった上、授業もろくに行っていませんでしたが、トライ式高等学院はそんな僕でもマンツーマンで指導をしてくれ、無事に三年間で卒業することができました。この学校を選ばなければ大学には進学できなかったでしょう。
| 募集定員 | キャンパスにより異なる |
| 偏差値 | なし(詳細) |
| 出願期間 | 公式サイトにてご確認ください |
| 選抜方法 | 面接+作文(一般入試のみ) |
| 進路内訳 | 卒業率:99.5%
*2022年3月卒業生の実績
大学進学率:69.7%
※大学進学率とは、進路決定者のうちの大学・短大・専門職大学に合格した者において。卒業/大学進学率2024年自社調べ。出典:文部科学省「学校基本調査」在籍生徒数3500人以上の通信制高校・サポート校において進学率全国1位。2023/3/23 産経メディックス調べ。令和4年度の学校基本調査:大学進学率23% |
| 国公立大学 | 東京大学/大阪大学/北海道大学/九州大学/神戸大学/筑波大学/金沢大学/広島大学/熊本大学/北海道教育大学/山形大学/東京学芸大学/電気通信大学/新潟大学/信州大学/静岡大学/福井大学/京都教育大学/京都工芸繊維大学/山口大学/愛媛大学/高知大学/長崎大学/鹿児島大学/琉球大学/前橋工科大学/東京都立大学/横浜市立大学/諏訪東京理科大学/愛知県立大学/神戸市外国語大学/兵庫県立大学/広島市立大学/北九州市立大学/熊本県立大学 ※2024年度大学入試の実績 |
| 私立大学 | 早稲田大学/慶應義塾大学/上智大学/東京理科大学/学習院大学/明治大学/青山学院大学/立教大学/中央大学/法政大学/関西学院大学/関西大学/同志社大学/立命館大学/日本大学/東洋大学/駒澤大学/専修大学/成城大学/成蹊大学/津田塾大学/南山大学/京都産業大学/近畿大学/甲南大学/龍谷大学/西南学院大学 ※2024年度大学入試の実績 |
 編集長 阪口
編集長 阪口
マンツーマンで指導が基本で、どんな状況の生徒でも柔軟に対応してもらえます。不登校や発達障害を持つ生徒、大学進学を考えている生徒に特におすすめです。
トライ式高等学院の資料を取り寄せる>>
長尾谷高等学校 卒業生の口コミ評判
4.4
5つ星中4.4つ星です!(5人の卒業生データ)
良かった点は簿記やマーケティングなどを学べた、アルバイトなど学業以外のことにも努力がしやすい
、授業以外の特別活動の選択肢が豊富、などです。
一方、悪かった点はコースなしのため友達ができにくい、うざい教師がいたことです。
卒業後の進路は軽い面談がある程度で自分から行動しない限りは親身になってくれません。良くも悪くも主体性が必要となる学校だと思います。
学校の雰囲気は普通の高校と同じで、気軽に先生に声をかけたりかけられたりと明るい雰囲気です。しかし、一回だけ教員同士が言い合いのような喧嘩をしていました。その時は少し不快な気分になりました。
もう一つ気になる点は、私が在籍しているときに赴任してきた体育教師が厳しく通信制の高校には合わない先生だと思いました。
通信制高校ではコミュニュケーションがうまく取れない生徒が多くいる中、昭和の体育教師が赴任してきたのは不思議に思いました。その他、面白くないイジりを教員にされたことがすごく不快で今でも思い出すとイライラします。
私は、もともと全日制に通っていました。しかし、自称進学校で、毎日勉強に追われて嫌気がさして、不登校になりました。
出席日数も足りなくなってきて、どうしようかと思ったとき、通信制高校の存在を知りました。
私が通っていた通信制高校の特徴は二つあります。
一つは夏休みや春休みがとにかく長いです。自由な時間が多いのでその間はアルバイトや趣味に使っていました。
二つ目は、各教科の単位取得に必要な出席日数も少ないことです。学校嫌いの私でも、難なく通うことができました。
私はなるべく早くスクーリングを終わらせたかったので、学期の前半は頑張って出席して、後半は学校にいかなくてもいいようにしてました。
これは私の例えすが、自分のライフスタイルに合わせて通うことができます。
考えられる懸念は、やはり交友関係が浅くなってしまうのではないかという点でしょうか。
私の高校では、特活と呼ばれる学校行事に参加できるので、そこで友達を作っている人もいました。でも私は友達を作ることに抵抗があったので、ドライな雰囲気も嫌いじゃなかったです。
私が通っていた高校は月に1回しか登校しなくてよくて本当に楽でした。残りの時間は自宅学習で宿題をやるというスタイルだったので一人でじっくりと考えながらゆっくりと学習することができ知識が血肉となったように思います。
先生も月に数回しか授業せず残りの時間はほとんど地域活動に参加してボランティアの掃除などをするという具合でしたのでゆったりとしており良かったと思います。質問にも気軽に応じてくれ学習もはかどりました。
来ている生徒には芸能人などもいて仲良くなれたりして良かったです。やはり月1回しか登校しないので時間の都合がつくというのが通信制高校最大のウリだと思います。
仕事しながら通っている人がほとんどでしたので学校は暇でもみんな忙しく生きていたようです。卒業後の進路は様々で大学に進む人や会社に勤める人、さらには芸能活動を続ける人や相撲部屋に進む人などいろんな人がいました。通信制なのでやはり変わった人が多かったように思います。
長尾谷高校は決まった授業時間を受け、レポートを提出。テストを受け、半年に1回繰り越しで1年間必要な単位を取得していく形です。金額は私立と同じぐらいと思います。メリットとしましては、服装・髪型の自由。年代も10代の子から50代の方がおられました。学校も1限だけ行って後はバイトに行けたり、この日にまとめて授業を受けようとか時間割を見ながら決めれるので融通がきくと思います。
デメリットは、学費が高いことと学割がきかない事です。生徒手帳はあるんですけど、電車の定期とかは毎日では無いので買えないです。体育の単位とるのも勉強とは違う場所の地域の公民館とかに行くので少し大変でした。ですが、遠足 校外学習 スキー宿泊とかもあり本人希望で行けるので思い出も作れて、個性も大切にしてくれるので楽しいです。先生も相談に乗ってくれて、私は1年休学して卒業までに4年かかりましたが、人間関係のトラブル等も無く、友達も出来て通信を選択して良かったなと考えています。
長尾谷高等学校は、通信制の高校なので月に数回しか登校する必要がありません。ほとんどの時間を自宅で課題レポートをやるという学習方法を採用しているため、人間関係のわずらわしさや満員電車に揺られての通学というものはほとんどありませんでした。ストレスなく快適に過ごせる高校だと思います。
月に数回課題レポートの提出のために登校する日も自由に選べますので、予定を自由に組めますので何にでもチャレンジすることができると思います。私は学外活動として掃除のボランティアをしておりましたが、地域住民の皆様と仲良くなる機会になりました。
学校の雰囲気も職員室には常時数人いるだけですし教室にもせいぜい10人20人いるぐらいですのでゆったりと温和な時間が流れています。先生はいつ行っても快く質問に応じてくれましたし、課題レポートの添削も言うことなしのきめ細かさでしたのでわかりやすいことこの上なしでした。卒業後の進路は様々で大学に行く人もいれば相撲部屋に入る人など変わった進路の人もいました。また社会人で中卒の人が高卒になりたくて来ている人もいました。
悪かった点は、自分で学習計画をたてて計画的に学習しなければ際限なくだらけてしまい、まともな学習ができないことです。ある程度目的意識のある、芯の強い方向けの学校になるかと思います。
この学校をレビューする
長尾谷高等学校ってどんな学校? 卒業生インタビュー

 卒業生
卒業生
こんにちは!長尾谷高等学校なんば校を卒業したコタロウです。
学校の雰囲気や設備はどんな感じ?と気になる方に向けて、「卒業生の本音」をお話していきます。学校選びの参考にしていただけると嬉しいです。
| 住所 | 〒556-0016大阪市浪速区元町1-11-1
JR・南海・近鉄・阪神・地下鉄難波(なんば)駅32番出口より350m |
|---|
| 通学コース | 海外語学スクーリングコース
公務員コース
スキルアップコース
ベーシックコース |
|---|
| 学費 | 入学金:50,000円
授業料:9,000円(履修1単位につき)
施設設備費:24,000円(年額)
特別活動費:12,000円(年額)
※ただし、入学月より月額1,000円
諸活動費:600円(年額)
卒業経費:7,000円(3年次のみ、寄贈品・アルバム代)
同窓会費:3,000円(3年次のみ) |
|---|
長尾谷高等学校(なんば校)は、大阪・難波という好立地条件で通学としても都心部に出る楽しさを含めて通いやすい場所にあります。スケジュールを自分で組み、大学生活を先取りするようなカリキュラムになっているので自分で動くことの大切さを学べます。
長尾谷高等学校(なんば校)の授業内容・時間割
 卒業生
卒業生長尾谷高等学校で学ぶ内容は、一般的な全日制高校と同じです。各学期終了時に規定の単位の習得が必要になるので、最低その単位を得るために出席しなければいけません。
もちろん全日程出席するのも可能。出席が困難な場合は自宅学習という完全な通信制もあります。年に二回のスクーリングのみの出席にも対応しているので自分の体力や気持ちと相談しながら通えます。
授業自体もハイスピードではなく、ゆっくりとひとつひとつ学ぶことができます。
また、自習室も常に解放されているので友達と一緒に勉強すること、食事をすることもできるので学校に行くこと学校に楽しいと思えるような環境になっています。
基本教科以外には体育も存在し、近くにある相撲の大会にも使われる大阪府立体育館を使用しての授業と、会場が豪華なのもポイント。体力を鍛える運動というよりはグループ分けされたスポーツを自分たちのペースですることができるので、いつも動かない分ちょっとしたリフレッシュ感覚で授業を受けられます。
基本的に強制されないのでその分自分で選んで学ぶことが大事です。
長尾谷高等学校(なんば校)の設備・学習環境はどう?
 卒業生
卒業生
なんば校は校舎自体はビルになるので決して広くありません。
教室ひとつずつにおいては一般的な高校のクラスの部屋と変わりはありません。一般の高校よりも一回の授業に出席する人数は少ない時が多いので窮屈感を感じることはありませんでした。
先生は単位制や通信制の学校にも関わらず一人一人認識するスピードも早く、積極的に話しかけてくださることが多いので自ずと会話をする機会も増えていきます。
勉強のことはもちろん、進学先の検討についても相談に積極的に乗ってくれる人たちが多い印象です。大学に行きたい、となれば学校の知識も多彩にお持ちなので色んな話を聞いてくれると思います。実際進学を希望して先生に相談に行く人たちはたくさんいました。
今作ることができる自分の学びに対するリズムを慣らしながら、将来を考える余裕を作れる場所と感じます。未来が見えなくても考える力と時間を見つけることができ、そのまま相談することができる相手がいる環境が長尾谷高等学校の魅力です。
長尾谷高等学校(なんば校)のイベントや学校行事
 卒業生
卒業生
基本的な大きいイベントはあまりありませんでした。なので、学生生活らしいもの、といえば経験していないのが現状です。
しかし、冬にはクリスマスパーティなど、ちょっとしたイベントは多く、授業で知り合った仲間と楽しんだり、その場で初めて会う人と友達になったりと学内の人に出会う小さなイベントは多々ありました。
それも長時間というわけではないので「ちょっと参加してみようかな」と気軽に飛び入りできるものです。途中退室もありなのでとても行きやすく感じました。
学園祭などはないので一般の人交えての機会というのは基本ありませんでした。そういうのが苦手だった私にとってはとても有り難かったです。
説明会や相談会については随時行っているようで、具体的な日にちは頻繁に取り上げられます。それ以外にも直接連絡を取れば個人での見学等も可能です。いつでも快く対応してくださるので気軽に一度、覗きにいってみるのも良いと思います。
長尾谷高等学校(なんば校)にいじめはある?学校の雰囲気について
 卒業生
卒業生
クラスという固定の枠はありませんので、授業に出席するたびメンバーが違うというのはいつものことでした。なので、いじめや喧嘩というものには一切出会ったことはありません。
それどころか話す機会を自ら作らなければあまりないので勇気を出して声をかける。そして友達になる。というケースが最も多くて、良い雰囲気な時ばかりでした。
生徒としては新学校を目指すからこそ一般の高校よりも時間に制限されない単位制を選んだ人や、仕事をしながら通っている人など様々です。一番多いのはやはり現役高校生。女の子が比率的には多いイメージでした。みんなアルバイトや本職をしながら通う凛々しい子たちばかりなので、しっかりした人たちが多かったように思えます。
長尾谷高等学校(なんば校) 卒業後の進路
 卒業生
卒業生
高卒認定が取れるということがあり、大学生活に進む人が多いです。そうでない人は真っ直ぐに就職していました。このどちらかが大半でした。
大学に進んだ人も実際その後働くことを既にイメージしながら大学選びをしていたので、偏差値の高い大学に進学する人もいましたし、就職に強い場所を厳選して選んで進学した人たちもいます。そのあたりの情報も先生たちは潤沢に揃えていらっしゃるので、そのサポートもあり全員スムーズに将来を決めていたと思います。
また、余裕ある学生生活の中で仕事に就きたいと考える人も多いので、正社員として、高卒で新入社員となり頑張って行く人たちもいました。私も兼ねてから好きだったファッションを活かすアパレル職に就職しました。
長尾谷高等学校(なんば校)の入学を検討している生徒へ
 卒業生
卒業生
毎日同じ場所に行き、同じ人たちの中で生活することに苦痛を感じる人はたくさんいると思います。
その中で我慢できるなら良いですが、そうじゃない人に「それを頑張らなくてもいい場所はあるんだよ」とこの学校を見て知ってほしいです。
でもそれは逃げでは決してなくて、「自分で自分のやることや自分の道を選ぶ」ということです。
それは普通にみんなと同じように過ごすよりも大変かもしれませんが、自分に余裕と自信もつきますし、何より毎日が楽しくなります。今の苦しい毎日を変えるために、一歩踏み出してみませんか?

通信制高校は学費が安い学校が多いですが、だからといってサポートが全くない学校を選んでしまうと、勉強をひとりで進めることができずに退学になってしまうケースもあります。
・まずは人気校の情報を取り寄せる
・近所の通信制高校もみてみる
・比較しながら子どもと相談して決める
という流れで学校選びを進めていきましょう。
\入学してから後悔しない/
まずは人気校の情報を取り寄せる

| 学費 | 73,000円〜(詳細)
*通信コース/就学支援金適用時
*通学にかかる費用はキャンパスによって異なります |
| スクーリング | 年間5日間~ |
| 開講コース | ネットコース/通学コース/オンライン通学コース/通学プログラミングコース |
| 入学時期 | 4月、7月、10月、1月 ※転入生は随時受け付け |
| 専門授業 | 語学/プログラミング/特進コース(キャンパスによる) |
| 本校所在地 | 沖縄県うるま市与那城伊計 24(入学は全国から可) |
| キャンパス | 札幌、仙台、東京(御茶ノ水・秋葉原・代々木・渋谷・池袋・立川・町田)、横浜、大宮、千葉、柏、名古屋、浜松、岐阜、新潟、金沢、大阪(天王寺・梅田・心斎橋)、神戸、姫路、京都、広島、高松、福岡、北九州、鹿児島他 |
| 募集人数 | |
| 偏差値 | なし(偏差値詳細) |
| 出願期間 | 参考:2023年度募集日程
第1期:2022/9/30-2022/11/1
第2期:2022/11/4-2022/12/6
第3期:2022/12/9-2023/1/10
第4期:2023/1/13-2023/2/14
第5期:2023/2/17-2023/3/7
第6期:2023/3/10-2023/3/22
※転編入は随時募集 |
| 選抜方法 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
課題作文・面接
【ネットコース】
書類選考 |
| 検定料 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
15,000円
【ネットコース】
10,000円(事務手数料代込み) |
2023年度
| 国公立大 | 東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学、広島大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、岩手大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、茨城大学、千葉大学、電気通信大学、東京外国語大学、東京藝術大学、東京農工大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、山梨大学、信州大学、静岡大学、岐阜大学、島根大学、山口大学、香川大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学他 |
| 私立大学 | 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、成城大学、成蹊大学、明治学院大学、國學院大学、武蔵大学、南山大学、立命館アジア太平洋大学、津田塾大学、東京女子大学、昭和女子大学、共立女子大学、大妻女子大学、同志社女子大学、京都女子大学、武庫川女子大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、神戸女学院大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学、東京造形大学他 |
| 海外大学 | トロント大学、マンチェスター大学、キングス・カレッジ・ロンドン、シドニー大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、モナシュ大学マレーシア校、ウィスコンシン大学マディソン校、オークランド大学、トリニティ・カレッジ (ダブリン大学)、ニューカッスル大学他 |
N高等学校の2023年度合格実績
N高等学校・S高等学校ってどんな学校? N高やS高をはじめて知る方へ
https://www.youtube.com/watch?v=mxZbTaYk8N0&t=3sネットの高校の部活動!日本全国の部員と交流する『ネット部活』
N高等学校・S高等学校 大学合格実績速報発表会
こちらの学校はいじめ・不登校などの問題を抱えた方に対するケアがしっかりとしているとのことで編入しました。実際、特に問題なく、先生方をはじめ学校側がすごくそのあたりをケアしているのが感じられました。
しかし、メンタル的なサポートをしっかりとしてくれるのは有り難いことですが、そういうサポートを受けなければ学校生活を送れないというコンプレックスを感じてしまいました。そういう意味では少し我慢して普通の高校に通ってもよかったのかなと思います。
学校や先生の雰囲気は非常に素晴らしいです。もともと、人間関係などの問題を抱えているという前提で向き合ってくれますので、通学することにストレスは感じませんでした。
進路に関しては正直、最初は不安でしたが、アニメが好きな知り合いがたくさん増えました。同じ趣味を持つ友人ができたので、将来はアニメ関係の道を目指せたらと思います。
人間関係などの不安で将来が心配な方は安心して通われて大丈夫だと思います。何より、同じ境遇や立場な方が多いので、自分が孤立しているという不安は解消できると思います。
N高等学校は1年目の評価が高いですなぜなら他の学校とは違うこいうことを実感できたからです違いとは、パソコンのスキル、Adobeのスキル、タイピングのスピードなどは他の学生よりも1年間で圧倒的に伸びたと感じますまた自由時間が多く(自分のやりたいことに取り組める時間)資格取得などにも取り組むことができました。
2年生からは1年生の時と同じような感じなのでこの制度にあき、N高でできる様々な課外活動系を重点的に取り組みましたそのおかげで日本、世界など様々なことが知れました(課外活動は全国各地、海外の課外活動もあります)。また短期で語学留学に行き様々な成長をすることができました。また予備校にも通い始め学力も伸びすごく充実していました(ちなみに2年生は週3です)
3年生では受験のため課外活動とかは一切せずに勉強に集中しました私はn高の場合いかに自立できるかで、評価が1~5は変動してくると感じます理由は宿題がなかったり、学校の中で自習の時間が1日の半分を占めるからです。
その時間を自分のためになる時間として使うかはたまたYouTube見てしまうか生徒の判断ですが自習の時間を活かせるかでN高を検討した方が私は良いと感じました自分のやりたいことをすでに持っている人にとってN高はお勧めできる価値のある学校だと感じます
良かった点私は人間関係の悩みでN高等学校に変えたので、まず人付き合いを強制されないというところにとても安心感を感じられ良かったです。
次にN高等学校のネットコースはとても登校日数が少ないので往復3時間かけていた登校時間の短縮が出来たことや、どんな時間でも好きなだけ授業動画を見ることが出来る機能があり、自分の集中出来るタイミングや自分のその時にできる量をやる事が出来たため、自由な時間がとても増えました。
その時間を使い、自分のスキルアップの時間を多く取る事が出来たのは今でもとてもよかったと感じています。
悪かった点ネットコースなので先生や他の生徒達との繋がりが弱いです。The高校生のような青春を送るのは少し難易度が高いと感じます。一応N高等学校には部活のようなチャットグループがあるのですが、キャンパスで面識があるお友達同士しか喋っていないことが多いので、ネットコースの人は上手くいかないこともあるかもしれません。
学校について私が言ったらキャンパスの建物はとても綺麗で、机等も使いやすい形でした。自動販売機等もあり不便さを感じることは無かったです。コロナ対策もしっかりしていて安心して登校する事が可能です。
結論から申し上げると、この高校に通うことができて本当に良かったと思います。学習面に関しては、自己管理能力や自己学習能力が求められますが、その点に関しては他の通信制高校でも大差はないと思います。
N高等学校の一番素晴らしかった点は、プログラムやイベントの多さです。投資部や起業部などの他の学校にはないユニークな部活があったり、ニコニコ動画を活用した大久保な文化祭が執り行われたりするなど、この高校でしかできない体験をたくさんすることができました。また、進路サポートも充実していて、国内の大学や専門学校進学に関する指導だけではなく、海外大学への出願サポートもあるため、さまざまな進路希望に対応してくれます。先生方は比較的若く、穏やかな方々が多い印象です。
中には学生時代不登校だった先生もいらっしゃるので、学校に生きづらいという生徒に寄り添ってくれる先生もいらっしゃいます。費用に関しては、週五日の通学コースだと本当に高いです。おそらく、全日制の私立高校よりも高いと思います。学費を節約したい場合は、ネットコースにして、オンライン上でさまざまな部活やイベントに参加するのがいいのではないかと思います。
よかった点は全日制の高校いってた時よりかは時間に縛られずノーストレスで家で学習していたところや、他の高校生と違い時間がありふれていたので、すきな趣味に没頭したり、今まで習ってきてなかったスキルを習得する時間を作れたことがよかったところです。
悪かった点は、全日制とは違い自宅にいる時間が多く、それと授業も先生方から渡された動画や課題をこなすだけだったので人とのコミュニケーションのできる場がなくて友達を作ろうにも作れない状況でした、ですが年に三回は指定された場所で授業をうけるのがあり、同じ気持ちをもってる優しい方もいれば、口が悪い子もいたりで微妙でした。
学校の先生の雰囲気は、誰よりも優しく、誰よりも相談に乗れる方々がいて疲れた心を癒してくれる場所でもありました。全日制の高校の先生なんか大抵が心がないやつしかいないので通信は優しい方がいっぱいいました。最後に迷ってる子がいるとしたら、通信も悪くない場所です!
 編集長 阪口
編集長 阪口
・学費が安い(年間10万円程度)
・生徒数日本No.1(=生徒が最も選んでいる通信制高校)
・東大・国立難関私大の合格実績多数
と学費の安さ、実績、学びやすさは日本トップ。通信制高校進学を考えたら、最初に検討したい学校です。
N高等学校の資料を取り寄せる>>

| 学費 | 一人ひとりに合わせて最適な料金プランを作成。
詳細は公式サイトでお問い合わせください。 |
| 開講コース | 【普通科】高校卒業を目指すコース
【特進科】大学進学を目指すコース |
| 入学時期 | 新入学:4月 10月 / 編入転入:随時 |
| 専門授業 | 特進科(大学進学コース) |
| 本校所在地 | 東京都千代田区飯田橋 1-10-3 |
| キャンパス | 全国に120キャンパス以上 |
評価的には4かなと思います。でもそこまで悪いところがあるわけでもないのですが、普通の高校の方がいい気がします。
良かった点は、ネットコースなのであまり人と会わないことです。正直人とのコミュニケーションなどは得意ではない方だったのでその方がありがたかったです。なので周りを気にせずに自分自身で勉強に取り組むことができたのでよかったです。
悪かった点としては、これをいうのもあれなんですが人とのコミュニケーションが取れないこと、そうなることで今後の社会に出た時などに人とのコミュニケーションは必ずと言って必要なものなので困りました。なので今でもネットを使ったような仕事をしていて人とあまり関わらないような仕事をしているので結果よかったか悪かったかわかりません。
今後このような通信制の学校などを考えているのであれば私なりには正直、普通の高校に通っていろんな人とコミュニケーションを取ることが大事になってくるのかなと思いました
まず、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、通信制教育に特化した学校です。自分のペースで学習が進められるため、仕事やアルバイト、病気や怪我などで通学が難しい場合でも、学業を続けることができます。また、進路に合わせてカリキュラムが選べるため、自分の目標に向かって無理なく学ぶことができます。
次に、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、豊富な教材や学習支援が用意されています。学習教材は、オンラインで提供されるため、自宅や外出先など、好きな場所で学習ができます。また、学習相談や質問に対する返信など、サポート体制も充実しており、生徒が不安なく学習を進めることができます。
さらに、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、先進的な取り組みが特徴です。例えば、AIを活用した学習支援システムが導入されており、生徒の学習状況を分析し、適切なアドバイスを出すことで、効率的な学習を促進しています。また、単位制度を採用しているため、必要な単位を取得することができれば、自由に卒業時期を選択できるなど、柔軟な学習スタイルをサポートしています。
最後に地域に根ざした学校として、地域との交流やボランティア活動に力を入れていることも魅力的です。例えば、地域の祭りやイベントに参加したり、老人ホームや児童福祉施設などでボランティア活動を行ったりすることで、社会貢献の意識を育てることができます。
トライ式高等学院の東京キャンパスは生徒数も多く、部活動や修学旅行、留学制度もあり、全日制高校と変わらない学校生活を送ることができました。大学受験に特化した特進科は先生が受験などのプランを立ててくださり、分からないところは丁寧に教えてくれます。全日制高校にはない、復習する授業もあり無事に第一志望の国公立大学に進むことができました。
欠点としては学費がとても高いことです。提携通信制高校の学費に加えてサポート費用がかかるため、年間学費は100-120万円ほどでした。一般の全日制高校+予備校にかかる費用と考えると相応かなとは思いますが、入学を希望する方は学費の把握はしておくようにしましょう。
僕は高校2年生ときに、私立の全日制高校から転入しました。その際不登校だったため、1年生の取得単位数は0でした。ですが、留年をしたくなかった僕は、留年せずに大学に進学できる学校を探している際にこの高校を見つけました。学力テストはいつもギリギリだった上、授業もろくに行っていませんでしたが、トライ式高等学院はそんな僕でもマンツーマンで指導をしてくれ、無事に三年間で卒業することができました。この学校を選ばなければ大学には進学できなかったでしょう。
| 募集定員 | キャンパスにより異なる |
| 偏差値 | なし(詳細) |
| 出願期間 | 公式サイトにてご確認ください |
| 選抜方法 | 面接+作文(一般入試のみ) |
| 進路内訳 | 卒業率:99.5%
*2022年3月卒業生の実績
大学進学率:69.7%
※大学進学率とは、進路決定者のうちの大学・短大・専門職大学に合格した者において。卒業/大学進学率2024年自社調べ。出典:文部科学省「学校基本調査」在籍生徒数3500人以上の通信制高校・サポート校において進学率全国1位。2023/3/23 産経メディックス調べ。令和4年度の学校基本調査:大学進学率23% |
| 国公立大学 | 東京大学/大阪大学/北海道大学/九州大学/神戸大学/筑波大学/金沢大学/広島大学/熊本大学/北海道教育大学/山形大学/東京学芸大学/電気通信大学/新潟大学/信州大学/静岡大学/福井大学/京都教育大学/京都工芸繊維大学/山口大学/愛媛大学/高知大学/長崎大学/鹿児島大学/琉球大学/前橋工科大学/東京都立大学/横浜市立大学/諏訪東京理科大学/愛知県立大学/神戸市外国語大学/兵庫県立大学/広島市立大学/北九州市立大学/熊本県立大学 ※2024年度大学入試の実績 |
| 私立大学 | 早稲田大学/慶應義塾大学/上智大学/東京理科大学/学習院大学/明治大学/青山学院大学/立教大学/中央大学/法政大学/関西学院大学/関西大学/同志社大学/立命館大学/日本大学/東洋大学/駒澤大学/専修大学/成城大学/成蹊大学/津田塾大学/南山大学/京都産業大学/近畿大学/甲南大学/龍谷大学/西南学院大学 ※2024年度大学入試の実績 |
 編集長 阪口
編集長 阪口
マンツーマンで指導が基本で、どんな状況の生徒でも柔軟に対応してもらえます。不登校や発達障害を持つ生徒、大学進学を考えている生徒に特におすすめです。
トライ式高等学院の資料を取り寄せる>>
 編集長 阪口
編集長 阪口 編集長 阪口
編集長 阪口



 編集長 阪口
編集長 阪口
 編集長 阪口
編集長 阪口
 編集長 阪口
編集長 阪口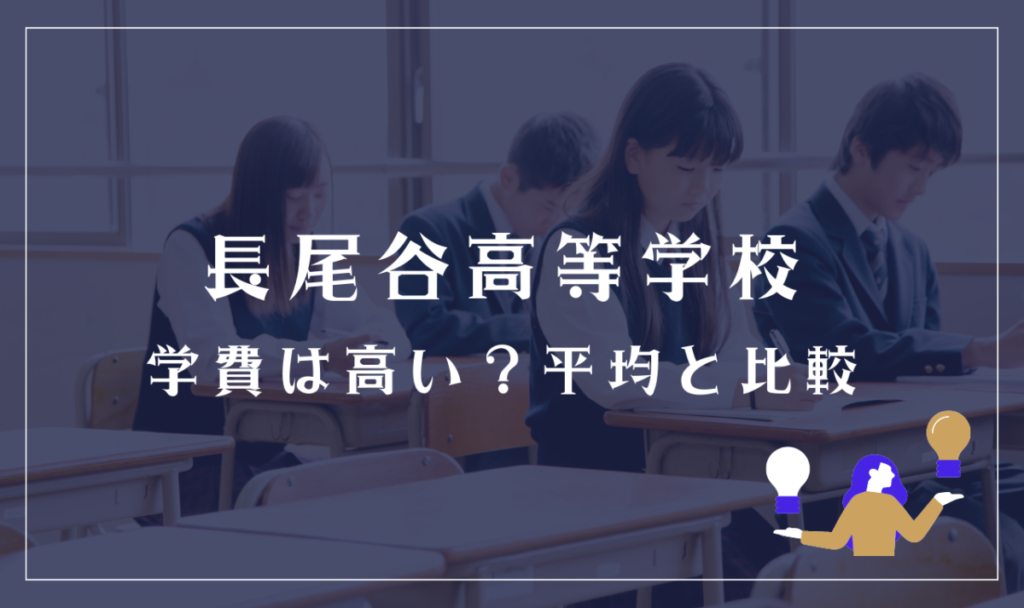
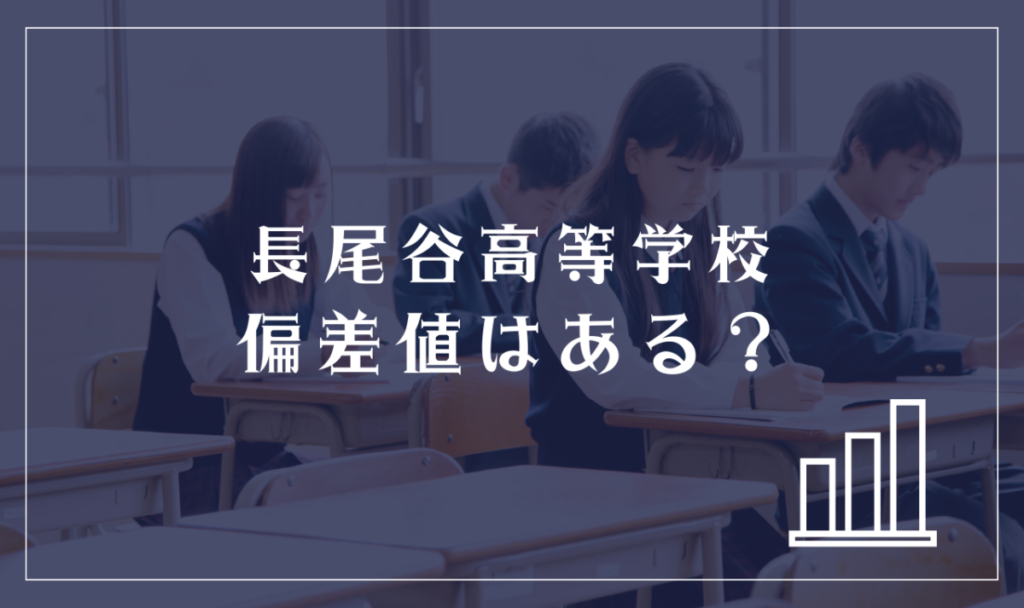
 編集長 阪口
編集長 阪口
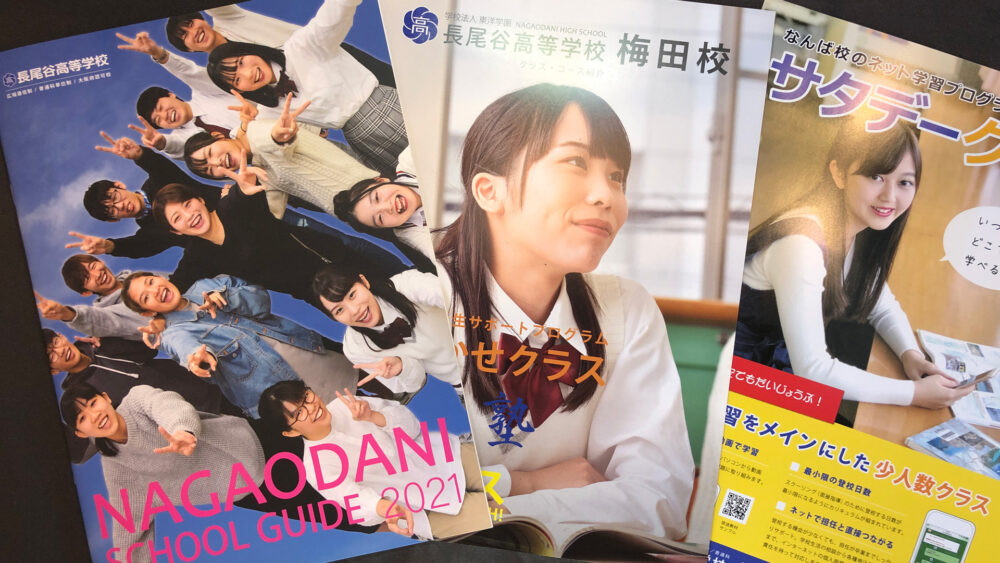
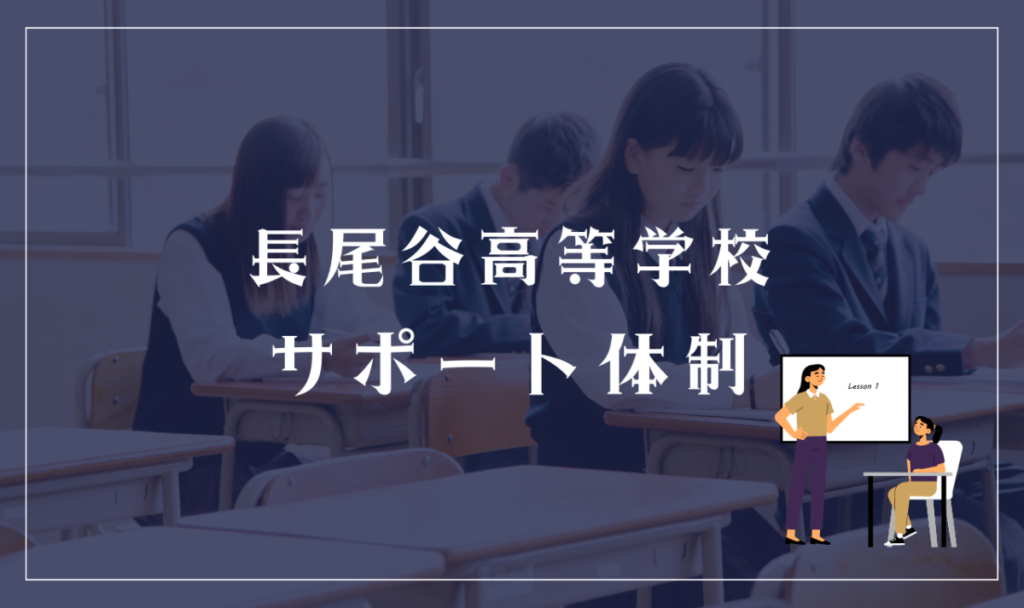
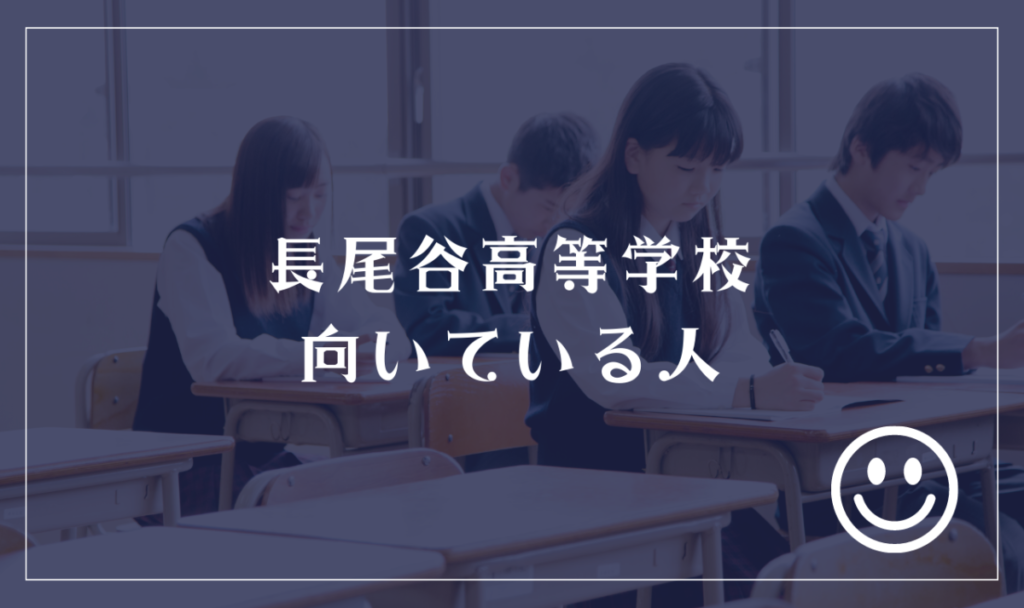
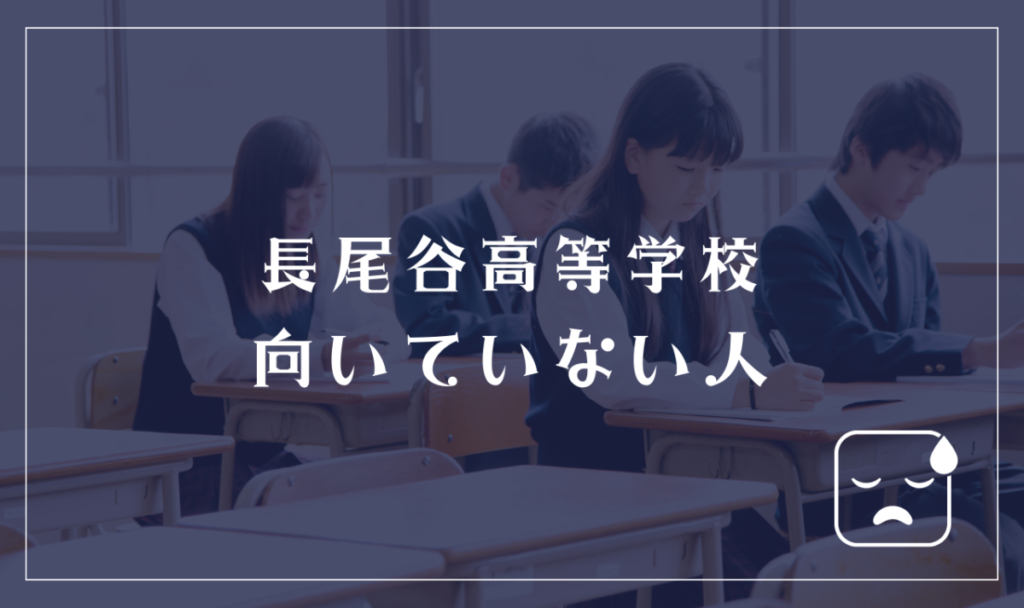
 編集長 阪口
編集長 阪口



 編集長 阪口
編集長 阪口
 編集長 阪口
編集長 阪口




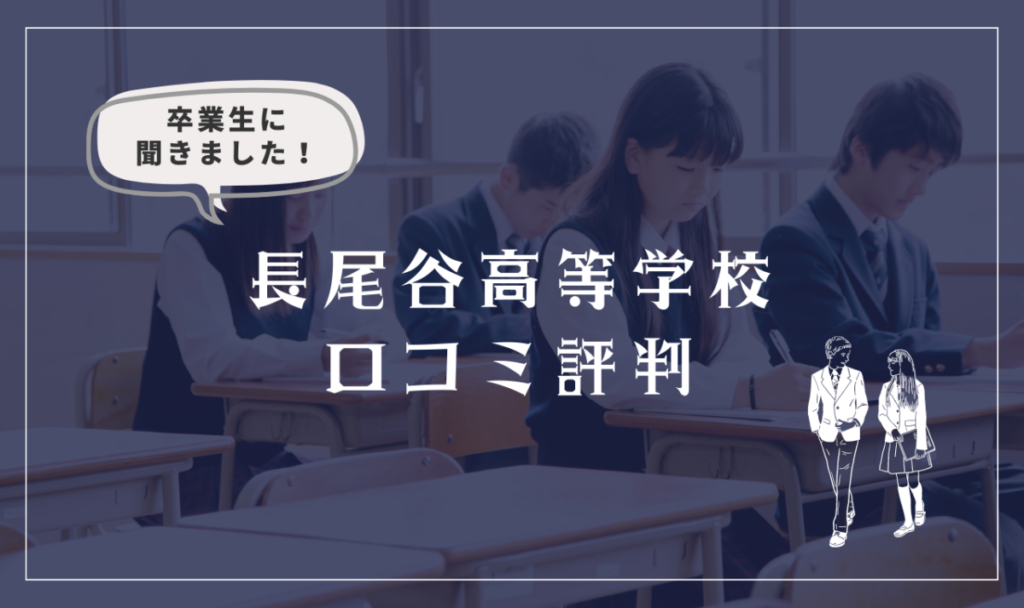
 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生



 編集長 阪口
編集長 阪口
 編集長 阪口
編集長 阪口