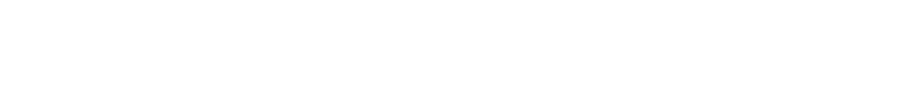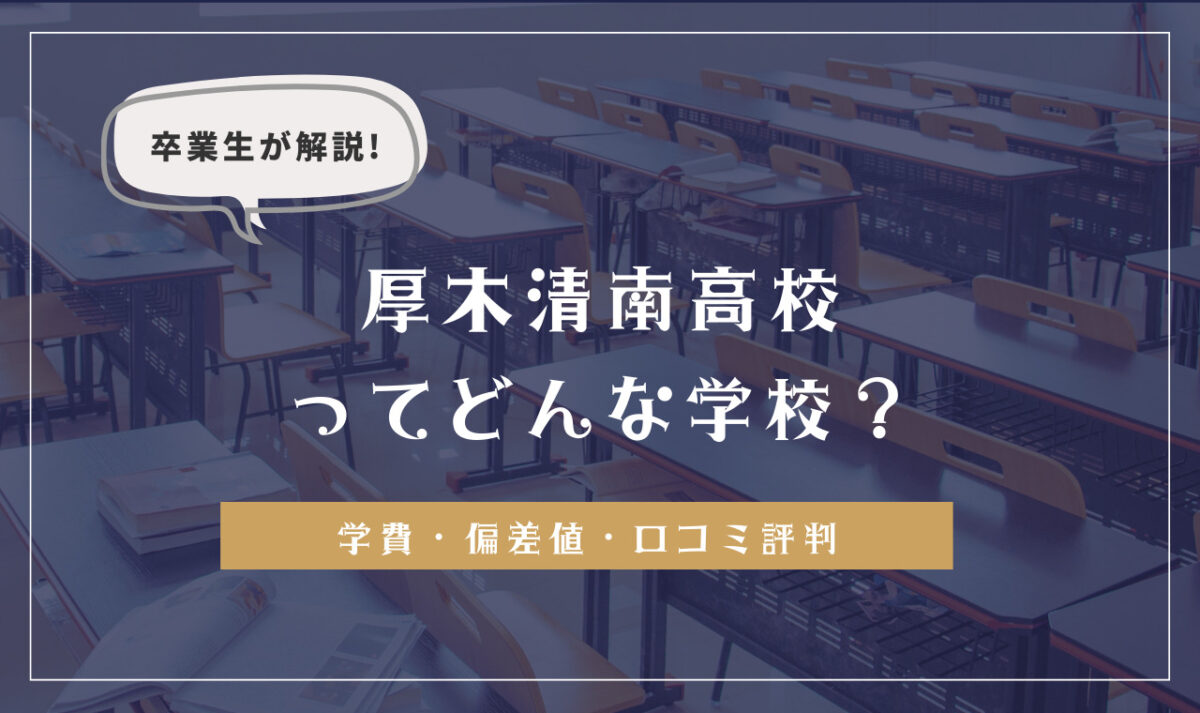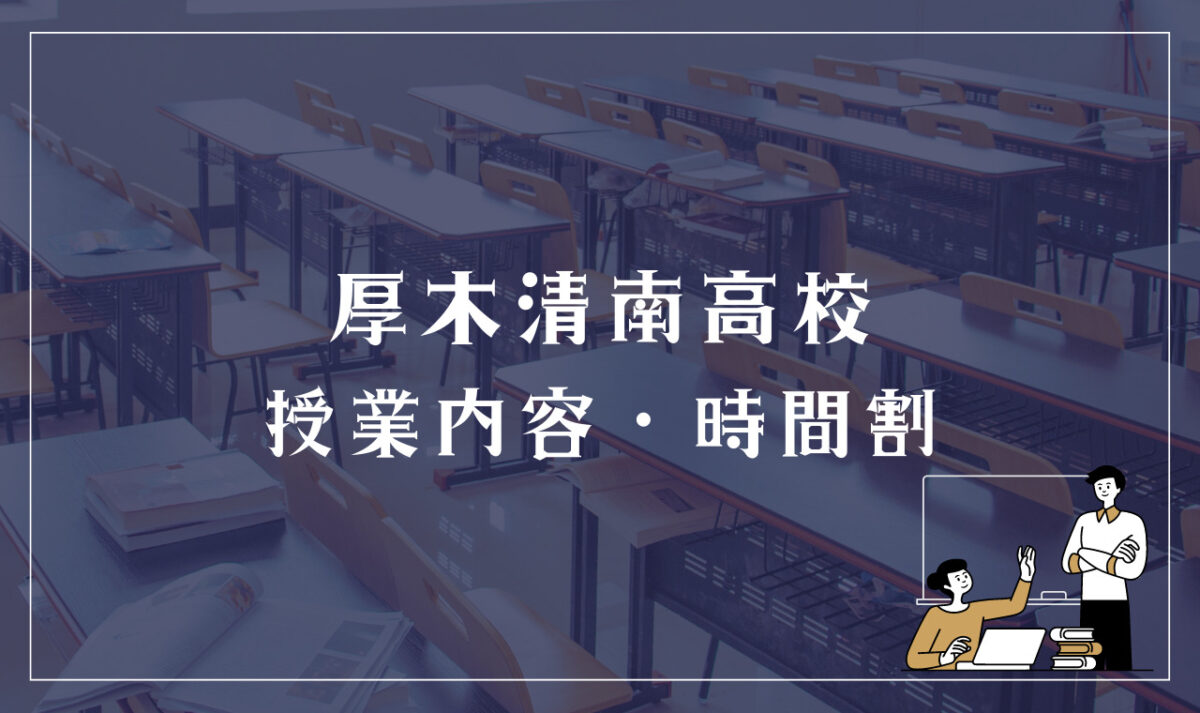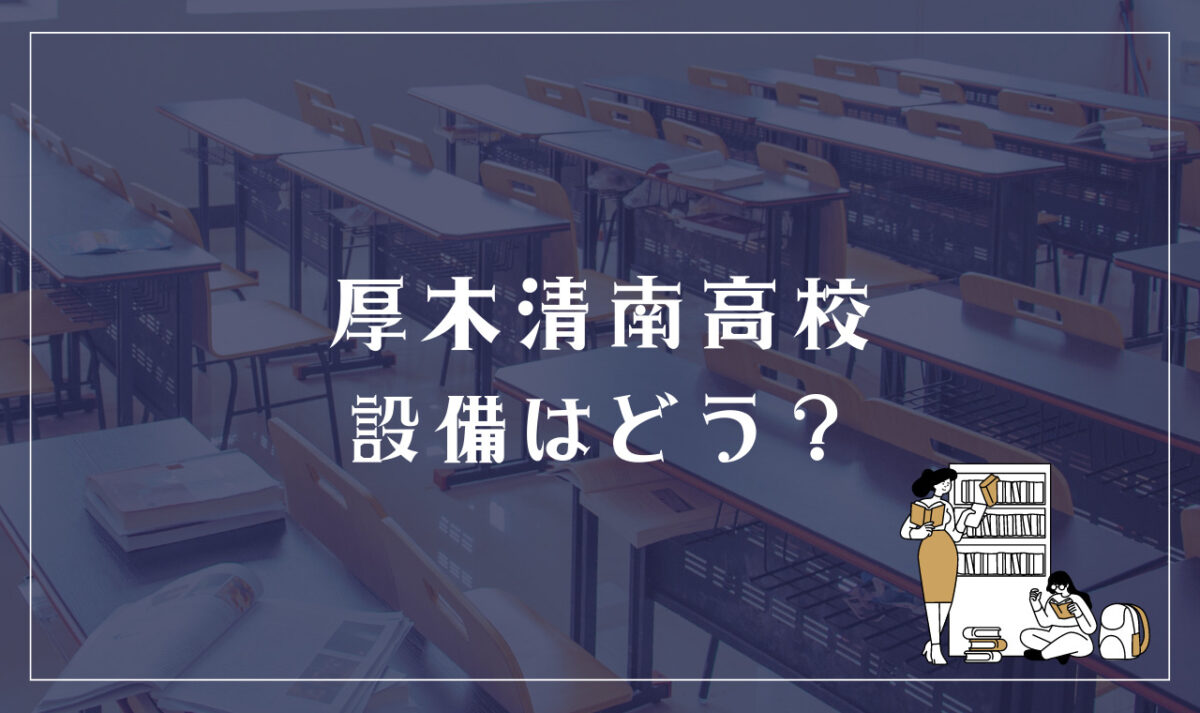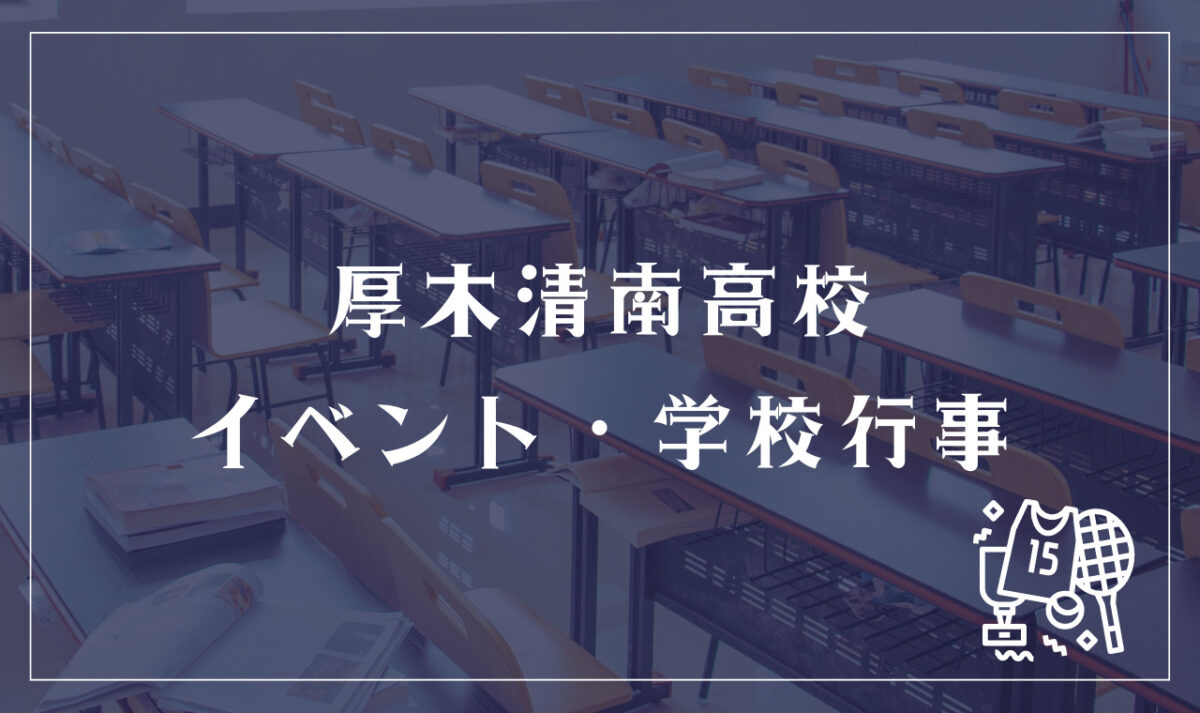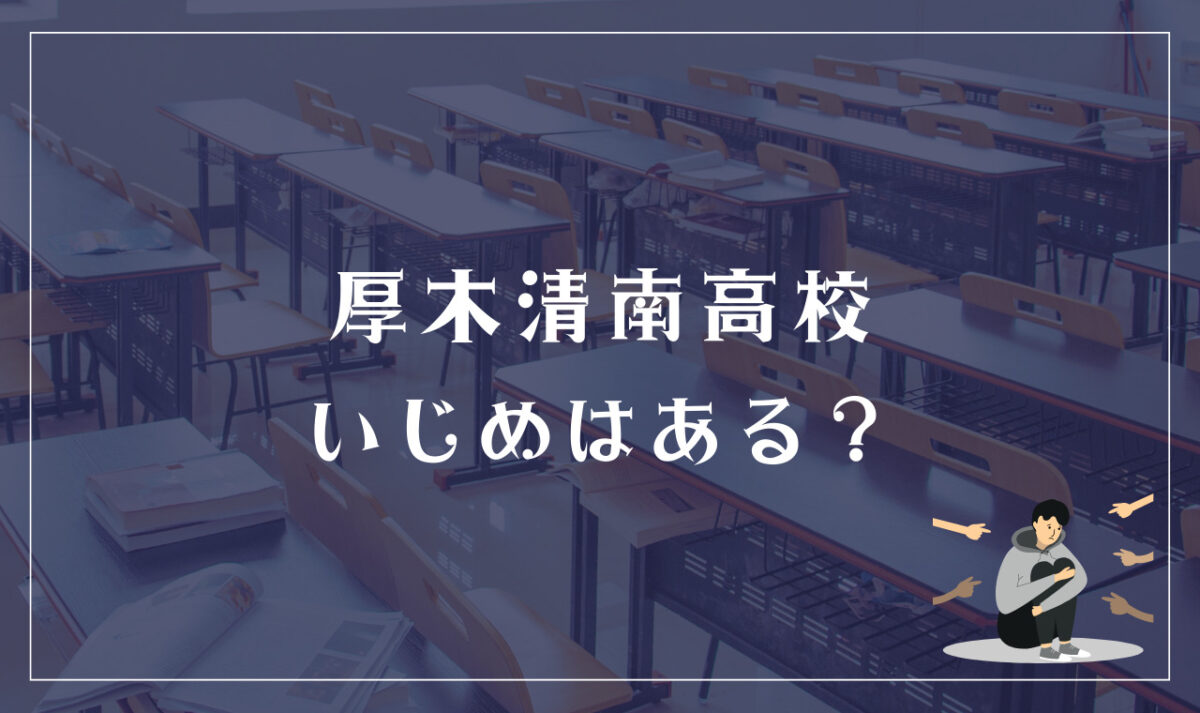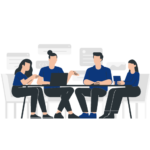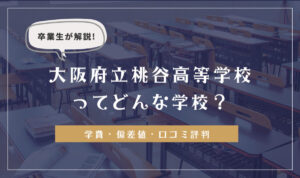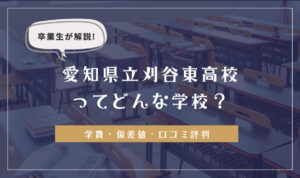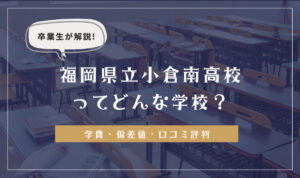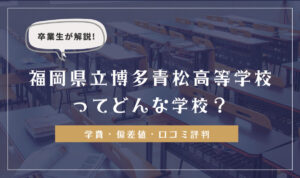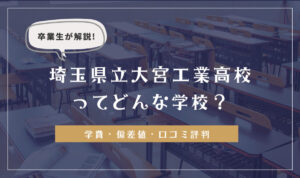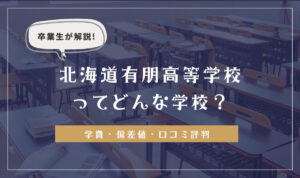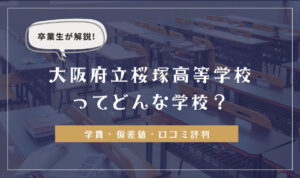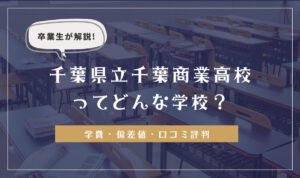厚木清南高等学校の学費
25,000円〜/年間
※就学支援金適用時の金額
※住所を入力すると近くの人気校資料をまとめて請求できます
 卒業生
卒業生
こんにちは、神奈川県立厚木清南高校(定時制)の通信制を卒業したユカです。
この記事では、旭陵高等学校(通信制)の雰囲気や学校の設備、学費について【卒業生の本音ベース】で解説しています。
学校選びの参考にしていただき、この学校に入学するかの判断基準にしていただければと思います。
定時制と合わせて通信制高校もみているけど、どちらがいいんだろう
3年通うところだし、学校選びで失敗したくないな・・・
 卒業生
卒業生
高校卒業資格は、定時制高校の他、通信制高校でも取得することができます。
定時制は通学が必要ですが、通信制は年数日〜週1日程度の通学で良いので、負担は少ないです。
定時制は卒業に4年かかる学校が多いですが、通信制は3年で済みます。比較する上でも、通える範囲にある通信制高校のパンフレットを合わせて請求するのがおすすめです。

通信制高校は学費が安い学校が多いですが、だからといってサポートが全くない学校を選んでしまうと、勉強をひとりで進めることができずに退学になってしまうケースもあります。
・まずは人気校の情報を取り寄せる
・近所の通信制高校もみてみる
・比較しながら子どもと相談して決める
という流れで学校選びを進めていきましょう。
\入学してから後悔しない/
まずは人気校の情報を取り寄せる

| 学費 | 73,000円〜(詳細)
*通信コース/就学支援金適用時
*通学にかかる費用はキャンパスによって異なります |
| スクーリング | 年間5日間~ |
| 開講コース | ネットコース/通学コース/オンライン通学コース/通学プログラミングコース |
| 入学時期 | 4月、7月、10月、1月 ※転入生は随時受け付け |
| 専門授業 | 語学/プログラミング/特進コース(キャンパスによる) |
| 本校所在地 | 沖縄県うるま市与那城伊計 24(入学は全国から可) |
| キャンパス | 札幌、仙台、東京(御茶ノ水・秋葉原・代々木・渋谷・池袋・立川・町田)、横浜、大宮、千葉、柏、名古屋、浜松、岐阜、新潟、金沢、大阪(天王寺・梅田・心斎橋)、神戸、姫路、京都、広島、高松、福岡、北九州、鹿児島他 |
| 募集人数 | |
| 偏差値 | なし(偏差値詳細) |
| 出願期間 | 参考:2023年度募集日程
第1期:2022/9/30-2022/11/1
第2期:2022/11/4-2022/12/6
第3期:2022/12/9-2023/1/10
第4期:2023/1/13-2023/2/14
第5期:2023/2/17-2023/3/7
第6期:2023/3/10-2023/3/22
※転編入は随時募集 |
| 選抜方法 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
課題作文・面接
【ネットコース】
書類選考 |
| 検定料 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
15,000円
【ネットコース】
10,000円(事務手数料代込み) |
2023年度
| 国公立大 | 東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学、広島大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、岩手大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、茨城大学、千葉大学、電気通信大学、東京外国語大学、東京藝術大学、東京農工大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、山梨大学、信州大学、静岡大学、岐阜大学、島根大学、山口大学、香川大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学他 |
| 私立大学 | 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、成城大学、成蹊大学、明治学院大学、國學院大学、武蔵大学、南山大学、立命館アジア太平洋大学、津田塾大学、東京女子大学、昭和女子大学、共立女子大学、大妻女子大学、同志社女子大学、京都女子大学、武庫川女子大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、神戸女学院大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学、東京造形大学他 |
| 海外大学 | トロント大学、マンチェスター大学、キングス・カレッジ・ロンドン、シドニー大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、モナシュ大学マレーシア校、ウィスコンシン大学マディソン校、オークランド大学、トリニティ・カレッジ (ダブリン大学)、ニューカッスル大学他 |
N高等学校の2023年度合格実績
N高等学校・S高等学校ってどんな学校? N高やS高をはじめて知る方へ
https://www.youtube.com/watch?v=mxZbTaYk8N0&t=3sネットの高校の部活動!日本全国の部員と交流する『ネット部活』
N高等学校・S高等学校 大学合格実績速報発表会
こちらの学校はいじめ・不登校などの問題を抱えた方に対するケアがしっかりとしているとのことで編入しました。実際、特に問題なく、先生方をはじめ学校側がすごくそのあたりをケアしているのが感じられました。
しかし、メンタル的なサポートをしっかりとしてくれるのは有り難いことですが、そういうサポートを受けなければ学校生活を送れないというコンプレックスを感じてしまいました。そういう意味では少し我慢して普通の高校に通ってもよかったのかなと思います。
学校や先生の雰囲気は非常に素晴らしいです。もともと、人間関係などの問題を抱えているという前提で向き合ってくれますので、通学することにストレスは感じませんでした。
進路に関しては正直、最初は不安でしたが、アニメが好きな知り合いがたくさん増えました。同じ趣味を持つ友人ができたので、将来はアニメ関係の道を目指せたらと思います。
人間関係などの不安で将来が心配な方は安心して通われて大丈夫だと思います。何より、同じ境遇や立場な方が多いので、自分が孤立しているという不安は解消できると思います。
N高等学校は1年目の評価が高いですなぜなら他の学校とは違うこいうことを実感できたからです違いとは、パソコンのスキル、Adobeのスキル、タイピングのスピードなどは他の学生よりも1年間で圧倒的に伸びたと感じますまた自由時間が多く(自分のやりたいことに取り組める時間)資格取得などにも取り組むことができました。
2年生からは1年生の時と同じような感じなのでこの制度にあき、N高でできる様々な課外活動系を重点的に取り組みましたそのおかげで日本、世界など様々なことが知れました(課外活動は全国各地、海外の課外活動もあります)。また短期で語学留学に行き様々な成長をすることができました。また予備校にも通い始め学力も伸びすごく充実していました(ちなみに2年生は週3です)
3年生では受験のため課外活動とかは一切せずに勉強に集中しました私はn高の場合いかに自立できるかで、評価が1~5は変動してくると感じます理由は宿題がなかったり、学校の中で自習の時間が1日の半分を占めるからです。
その時間を自分のためになる時間として使うかはたまたYouTube見てしまうか生徒の判断ですが自習の時間を活かせるかでN高を検討した方が私は良いと感じました自分のやりたいことをすでに持っている人にとってN高はお勧めできる価値のある学校だと感じます
良かった点私は人間関係の悩みでN高等学校に変えたので、まず人付き合いを強制されないというところにとても安心感を感じられ良かったです。
次にN高等学校のネットコースはとても登校日数が少ないので往復3時間かけていた登校時間の短縮が出来たことや、どんな時間でも好きなだけ授業動画を見ることが出来る機能があり、自分の集中出来るタイミングや自分のその時にできる量をやる事が出来たため、自由な時間がとても増えました。
その時間を使い、自分のスキルアップの時間を多く取る事が出来たのは今でもとてもよかったと感じています。
悪かった点ネットコースなので先生や他の生徒達との繋がりが弱いです。The高校生のような青春を送るのは少し難易度が高いと感じます。一応N高等学校には部活のようなチャットグループがあるのですが、キャンパスで面識があるお友達同士しか喋っていないことが多いので、ネットコースの人は上手くいかないこともあるかもしれません。
学校について私が言ったらキャンパスの建物はとても綺麗で、机等も使いやすい形でした。自動販売機等もあり不便さを感じることは無かったです。コロナ対策もしっかりしていて安心して登校する事が可能です。
結論から申し上げると、この高校に通うことができて本当に良かったと思います。学習面に関しては、自己管理能力や自己学習能力が求められますが、その点に関しては他の通信制高校でも大差はないと思います。
N高等学校の一番素晴らしかった点は、プログラムやイベントの多さです。投資部や起業部などの他の学校にはないユニークな部活があったり、ニコニコ動画を活用した大久保な文化祭が執り行われたりするなど、この高校でしかできない体験をたくさんすることができました。また、進路サポートも充実していて、国内の大学や専門学校進学に関する指導だけではなく、海外大学への出願サポートもあるため、さまざまな進路希望に対応してくれます。先生方は比較的若く、穏やかな方々が多い印象です。
中には学生時代不登校だった先生もいらっしゃるので、学校に生きづらいという生徒に寄り添ってくれる先生もいらっしゃいます。費用に関しては、週五日の通学コースだと本当に高いです。おそらく、全日制の私立高校よりも高いと思います。学費を節約したい場合は、ネットコースにして、オンライン上でさまざまな部活やイベントに参加するのがいいのではないかと思います。
よかった点は全日制の高校いってた時よりかは時間に縛られずノーストレスで家で学習していたところや、他の高校生と違い時間がありふれていたので、すきな趣味に没頭したり、今まで習ってきてなかったスキルを習得する時間を作れたことがよかったところです。
悪かった点は、全日制とは違い自宅にいる時間が多く、それと授業も先生方から渡された動画や課題をこなすだけだったので人とのコミュニケーションのできる場がなくて友達を作ろうにも作れない状況でした、ですが年に三回は指定された場所で授業をうけるのがあり、同じ気持ちをもってる優しい方もいれば、口が悪い子もいたりで微妙でした。
学校の先生の雰囲気は、誰よりも優しく、誰よりも相談に乗れる方々がいて疲れた心を癒してくれる場所でもありました。全日制の高校の先生なんか大抵が心がないやつしかいないので通信は優しい方がいっぱいいました。最後に迷ってる子がいるとしたら、通信も悪くない場所です!
 編集長 阪口
編集長 阪口
・学費が安い(年間10万円程度)
・生徒数日本No.1(=生徒が最も選んでいる通信制高校)
・東大・国立難関私大の合格実績多数
と学費の安さ、実績、学びやすさは日本トップ。通信制高校進学を考えたら、最初に検討したい学校です。
N高等学校の資料を取り寄せる>>

| 学費 | 一人ひとりに合わせて最適な料金プランを作成。
詳細は公式サイトでお問い合わせください。 |
| 開講コース | 【普通科】高校卒業を目指すコース
【特進科】大学進学を目指すコース |
| 入学時期 | 新入学:4月 10月 / 編入転入:随時 |
| 専門授業 | 特進科(大学進学コース) |
| 本校所在地 | 東京都千代田区飯田橋 1-10-3 |
| キャンパス | 全国に120キャンパス以上 |
評価的には4かなと思います。でもそこまで悪いところがあるわけでもないのですが、普通の高校の方がいい気がします。
良かった点は、ネットコースなのであまり人と会わないことです。正直人とのコミュニケーションなどは得意ではない方だったのでその方がありがたかったです。なので周りを気にせずに自分自身で勉強に取り組むことができたのでよかったです。
悪かった点としては、これをいうのもあれなんですが人とのコミュニケーションが取れないこと、そうなることで今後の社会に出た時などに人とのコミュニケーションは必ずと言って必要なものなので困りました。なので今でもネットを使ったような仕事をしていて人とあまり関わらないような仕事をしているので結果よかったか悪かったかわかりません。
今後このような通信制の学校などを考えているのであれば私なりには正直、普通の高校に通っていろんな人とコミュニケーションを取ることが大事になってくるのかなと思いました
まず、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、通信制教育に特化した学校です。自分のペースで学習が進められるため、仕事やアルバイト、病気や怪我などで通学が難しい場合でも、学業を続けることができます。また、進路に合わせてカリキュラムが選べるため、自分の目標に向かって無理なく学ぶことができます。
次に、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、豊富な教材や学習支援が用意されています。学習教材は、オンラインで提供されるため、自宅や外出先など、好きな場所で学習ができます。また、学習相談や質問に対する返信など、サポート体制も充実しており、生徒が不安なく学習を進めることができます。
さらに、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、先進的な取り組みが特徴です。例えば、AIを活用した学習支援システムが導入されており、生徒の学習状況を分析し、適切なアドバイスを出すことで、効率的な学習を促進しています。また、単位制度を採用しているため、必要な単位を取得することができれば、自由に卒業時期を選択できるなど、柔軟な学習スタイルをサポートしています。
最後に地域に根ざした学校として、地域との交流やボランティア活動に力を入れていることも魅力的です。例えば、地域の祭りやイベントに参加したり、老人ホームや児童福祉施設などでボランティア活動を行ったりすることで、社会貢献の意識を育てることができます。
トライ式高等学院の東京キャンパスは生徒数も多く、部活動や修学旅行、留学制度もあり、全日制高校と変わらない学校生活を送ることができました。大学受験に特化した特進科は先生が受験などのプランを立ててくださり、分からないところは丁寧に教えてくれます。全日制高校にはない、復習する授業もあり無事に第一志望の国公立大学に進むことができました。
欠点としては学費がとても高いことです。提携通信制高校の学費に加えてサポート費用がかかるため、年間学費は100-120万円ほどでした。一般の全日制高校+予備校にかかる費用と考えると相応かなとは思いますが、入学を希望する方は学費の把握はしておくようにしましょう。
僕は高校2年生ときに、私立の全日制高校から転入しました。その際不登校だったため、1年生の取得単位数は0でした。ですが、留年をしたくなかった僕は、留年せずに大学に進学できる学校を探している際にこの高校を見つけました。学力テストはいつもギリギリだった上、授業もろくに行っていませんでしたが、トライ式高等学院はそんな僕でもマンツーマンで指導をしてくれ、無事に三年間で卒業することができました。この学校を選ばなければ大学には進学できなかったでしょう。
| 募集定員 | キャンパスにより異なる |
| 偏差値 | なし(詳細) |
| 出願期間 | 公式サイトにてご確認ください |
| 選抜方法 | 面接+作文(一般入試のみ) |
| 進路内訳 | 卒業率:99.5%
*2022年3月卒業生の実績
大学進学率:69.7%
※大学進学率とは、進路決定者のうちの大学・短大・専門職大学に合格した者において。卒業/大学進学率2024年自社調べ。出典:文部科学省「学校基本調査」在籍生徒数3500人以上の通信制高校・サポート校において進学率全国1位。2023/3/23 産経メディックス調べ。令和4年度の学校基本調査:大学進学率23% |
| 国公立大学 | 東京大学/大阪大学/北海道大学/九州大学/神戸大学/筑波大学/金沢大学/広島大学/熊本大学/北海道教育大学/山形大学/東京学芸大学/電気通信大学/新潟大学/信州大学/静岡大学/福井大学/京都教育大学/京都工芸繊維大学/山口大学/愛媛大学/高知大学/長崎大学/鹿児島大学/琉球大学/前橋工科大学/東京都立大学/横浜市立大学/諏訪東京理科大学/愛知県立大学/神戸市外国語大学/兵庫県立大学/広島市立大学/北九州市立大学/熊本県立大学 ※2024年度大学入試の実績 |
| 私立大学 | 早稲田大学/慶應義塾大学/上智大学/東京理科大学/学習院大学/明治大学/青山学院大学/立教大学/中央大学/法政大学/関西学院大学/関西大学/同志社大学/立命館大学/日本大学/東洋大学/駒澤大学/専修大学/成城大学/成蹊大学/津田塾大学/南山大学/京都産業大学/近畿大学/甲南大学/龍谷大学/西南学院大学 ※2024年度大学入試の実績 |
 編集長 阪口
編集長 阪口
マンツーマンで指導が基本で、どんな状況の生徒でも柔軟に対応してもらえます。不登校や発達障害を持つ生徒、大学進学を考えている生徒に特におすすめです。
トライ式高等学院の資料を取り寄せる>>
目次
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)ってどんな学校?

厚木清南高等学校は「フレキシブルスクール」として生徒の自主性を育むような学校です。神奈川県内にある公立高校で、通信制、全日制、定時制の3つの課程があります。
多彩な科目の中から自身で時間割を決め、オリジナルの時間割を計画します。1年間で取得する単位の数も自分次第です。1年目はゆっくりスタートし、後半から本気を出すスタイルでも自由です。
また、3課程あるため、様々な生徒のスタイルに対応しやすくなっており、講義によっては野外授業も行っているので、より学習しやすい環境で受講できます。
神奈川県立厚木清南高校(定時制)の学費・授業料
 神奈川県立厚木清南高校の学費は次のとおりです。県立高校の授業料、入学検定料、入学料は条例により定められています。
神奈川県立厚木清南高校の学費は次のとおりです。県立高校の授業料、入学検定料、入学料は条例により定められています。
- 入学検査料:0円
- 入学料:0円
- 受講料:1単位350円 (平日登校履修の場合は700円)
ここから就学支援金が差し引かれ、授業料は実質無料となります。
教科書代などは受講する科目によって異なりますが、だいたい年間の支払い総額は【25,000円程度/年】となります。
更にすでに社会人として働いている生徒には、教科書等の代金が後日還付される制度があります。この制度の活用により少ない負担で学習を続けることができます。これとは別に、協力校や本校に行くときの交通費がかかります。
神奈川県立厚木清南高校(定時制)に偏差値はある?

定時制高校は希望をすれば誰でも入学することができるので「偏差値」と呼ばれる基準はありません。
入学願書は12月初旬〜3月中旬まで配布されますが、直接本校まで取りに行く必要があります。
2月27日に行われる学校説明会のついでに受け取るのがオススメです。
厚木清南高校の入試問題
入学選考は作文です。
- 入学希望の動機
- 本校の通信制に対する理解度
- 高校生活に対する意欲
- 将来の希望
以上4つのテーマに沿って記述します。自分の意見を文章で表現できるようになっておきましょう。
受け入れ人数にも限りがありますので注意してください。多数の申し込みが合った場合は作文の出来次第では落ちる可能性があるかもしれません。
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)の授業内容・時間割

私は定時制の4年間での卒業予定で入学しました。
定時制とは、夜間高校と称されることもありますが、基本的に夕方から夜の時間帯に通学するスタイルの事です。
清南高校では、在籍年数が3年間と4年間で選択できるのですが、3年制ですと、1日の受講数が増えるという仕組みです。
前期と後期に分けられていて、それぞれ期末テストがあります。取得単位の計算もこのタイミングで行われるので、前期に○単位、後期に○単位といった認識でいる生徒が多かったと感じます。
厚木清南高等学校の時間割
時間割は、1年生の前期のみ決まっていて、後期からは自分たちで作成しました。
例外はありますが、基本的に1,2限は全日制の時間になるので、定時制生徒は通学しません。ですので、授業はお昼過ぎから夜にかけての時間割が選べます。(3限~6限)
上記にもあるように、私は4年間だったので、授業は基本的に5、6限のみでした。
時間帯は17:30~19:00までが5限、19:00~19:20までが休み時間、6限は19:25~20:55までです。
部活に入っている生徒はその後22:00頃まで練習等を行います。
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)の設備・学習環境はどう?

キャンパス内は比較的きれいな学校だったと記憶しています。
来客や車いすの生徒のためにエレベーターは完備、図書室も幅広いジャンルの書籍が並んでおり、視聴覚室は、どの席からも正面が見やすいように整備されています。
教室自体は広くもなく、狭くもなくといったところでしょう。黒板や教壇等も一般的な大きさです。ただ、私が受講していた物理の教室は黒板が大きく、教室自体も広めに設置されていました。
一クラス大体40人くらいで5~6のクラス数だったと思いますが、4年生になると3年で卒業の生徒がいなくなるので、例年生徒数もクラスの数も、もっと少なくなります。
専門といえる授業はあまり受けなかったのですが、習字に関しましては先生は丁寧でした。一応書道室での授業でしたが、割と普通の教室に近いような環境です。
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)のイベントや学校行事

清南高校では季節により、様々なイベントが行われます。
また、参加することにより、LHR(ロングホームルーム)という授業への出席扱いになるイベントもありました。
LHRとは、毎週木曜日に設定されている授業で、普段はそれぞれの授業へ出席しているクラスメイトが教室へ集まります。この時間に、進路についての講義や、文化祭の準備などをします。
文化祭やスポーツ大会も、全日制と同じように行われます。ですが、普段全日制と定時制は教室を共有しているため、文化祭の時には全日制が教室を使っていました。その代わりに定時制の生徒は学校の中庭が使えたので、そこで出し物を行いました。
出し物の数としては、学年につき3つほどだったかなという記憶です。クラスでというより、学年全体で団結するというイメージの方が近いでしょう。
他のイベントとしては、野外学習の一環で、動物園や横浜観光などへ出向くこともありました。こちらも事前にLHRでグループになり、当日の予定を決めたりします。
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)にいじめはある?学校の雰囲気について

学校全体の雰囲気としては、3つの課程が揃っているので、比較的賑やかな雰囲気でした。あまり生徒同士で会話をしたがらない子などもおり、色々な生徒がいるので一概には言えませんが、基本的には皆仲が良く、明るいイメージが強い学校でした。
時間割を個々で決め、それぞれ授業を受けるというシステム上、どちらかというとそこまで干渉し合う環境では無いのではと感じます。
クラス全体の仲は悪くないが、必要以上に深く関わることもない、といった雰囲気です。
やはり多少のグループは出来ていて、それぞれで仲良くする、というイメージが近いですね。
もちろん個人同士ではまれにトラブルが生まれてしまう事もあるかもしれませんが、私の知る限りではいじめ等はなく、それぞれ仲が良い子同士関係を深めていた印象です。
また、生活指導の先生も担当で決められているので、安心出来るかと思います。
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)卒業後の進路

 卒業生
卒業生
私は、専門学校等への進学も進められたのですが、フリーターになることを選びました。
理由はどうしてもやってみたい仕事があり、あまり正社員では募集していない業種だったからです。
また、担任の先生には専門学校に行きながらでも良いのではと言われましたが、当時はお金をかけてまでやりたいことが見つからなかったので、断りました。
このような例もあるのですが、進路を考え始める時期になると、担任との面談の機会も設けられるので、しっかりと向き合うことが出来るかと思います。
他の生徒の進路は、私の周りでは、専門学校へ行く子が多かったかなという印象です。
また、先程も記述しましたが、LHRで色々な職業の説明を聞けることもあるので、もちろん就職を目指すことも出来ます。
神奈川県立厚木清南高等学校(定時制)を目指す方へ
清南高校の定時制は、自分のペースで学びたいという方や、中学校でちょっと躓いてしまった、というような生徒には比較的あっているのではと感じます。
また、昼間働いている方や、大人になってから高卒の資格が必要になった、といった方にもおすすめです!

通信制高校は学費が安い学校が多いですが、だからといってサポートが全くない学校を選んでしまうと、勉強をひとりで進めることができずに退学になってしまうケースもあります。
・まずは人気校の情報を取り寄せる
・近所の通信制高校もみてみる
・比較しながら子どもと相談して決める
という流れで学校選びを進めていきましょう。
\入学してから後悔しない/
まずは人気校の情報を取り寄せる

| 学費 | 73,000円〜(詳細)
*通信コース/就学支援金適用時
*通学にかかる費用はキャンパスによって異なります |
| スクーリング | 年間5日間~ |
| 開講コース | ネットコース/通学コース/オンライン通学コース/通学プログラミングコース |
| 入学時期 | 4月、7月、10月、1月 ※転入生は随時受け付け |
| 専門授業 | 語学/プログラミング/特進コース(キャンパスによる) |
| 本校所在地 | 沖縄県うるま市与那城伊計 24(入学は全国から可) |
| キャンパス | 札幌、仙台、東京(御茶ノ水・秋葉原・代々木・渋谷・池袋・立川・町田)、横浜、大宮、千葉、柏、名古屋、浜松、岐阜、新潟、金沢、大阪(天王寺・梅田・心斎橋)、神戸、姫路、京都、広島、高松、福岡、北九州、鹿児島他 |
| 募集人数 | |
| 偏差値 | なし(偏差値詳細) |
| 出願期間 | 参考:2023年度募集日程
第1期:2022/9/30-2022/11/1
第2期:2022/11/4-2022/12/6
第3期:2022/12/9-2023/1/10
第4期:2023/1/13-2023/2/14
第5期:2023/2/17-2023/3/7
第6期:2023/3/10-2023/3/22
※転編入は随時募集 |
| 選抜方法 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
課題作文・面接
【ネットコース】
書類選考 |
| 検定料 | 【通学コース・通学プログラミングコース】
15,000円
【ネットコース】
10,000円(事務手数料代込み) |
2023年度
| 国公立大 | 東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、九州大学、東京工業大学、一橋大学、広島大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、岩手大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、茨城大学、千葉大学、電気通信大学、東京外国語大学、東京藝術大学、東京農工大学、横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、山梨大学、信州大学、静岡大学、岐阜大学、島根大学、山口大学、香川大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学他 |
| 私立大学 | 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、成城大学、成蹊大学、明治学院大学、國學院大学、武蔵大学、南山大学、立命館アジア太平洋大学、津田塾大学、東京女子大学、昭和女子大学、共立女子大学、大妻女子大学、同志社女子大学、京都女子大学、武庫川女子大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、神戸女学院大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学、東京造形大学他 |
| 海外大学 | トロント大学、マンチェスター大学、キングス・カレッジ・ロンドン、シドニー大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、モナシュ大学マレーシア校、ウィスコンシン大学マディソン校、オークランド大学、トリニティ・カレッジ (ダブリン大学)、ニューカッスル大学他 |
N高等学校の2023年度合格実績
N高等学校・S高等学校ってどんな学校? N高やS高をはじめて知る方へ
https://www.youtube.com/watch?v=mxZbTaYk8N0&t=3sネットの高校の部活動!日本全国の部員と交流する『ネット部活』
N高等学校・S高等学校 大学合格実績速報発表会
こちらの学校はいじめ・不登校などの問題を抱えた方に対するケアがしっかりとしているとのことで編入しました。実際、特に問題なく、先生方をはじめ学校側がすごくそのあたりをケアしているのが感じられました。
しかし、メンタル的なサポートをしっかりとしてくれるのは有り難いことですが、そういうサポートを受けなければ学校生活を送れないというコンプレックスを感じてしまいました。そういう意味では少し我慢して普通の高校に通ってもよかったのかなと思います。
学校や先生の雰囲気は非常に素晴らしいです。もともと、人間関係などの問題を抱えているという前提で向き合ってくれますので、通学することにストレスは感じませんでした。
進路に関しては正直、最初は不安でしたが、アニメが好きな知り合いがたくさん増えました。同じ趣味を持つ友人ができたので、将来はアニメ関係の道を目指せたらと思います。
人間関係などの不安で将来が心配な方は安心して通われて大丈夫だと思います。何より、同じ境遇や立場な方が多いので、自分が孤立しているという不安は解消できると思います。
N高等学校は1年目の評価が高いですなぜなら他の学校とは違うこいうことを実感できたからです違いとは、パソコンのスキル、Adobeのスキル、タイピングのスピードなどは他の学生よりも1年間で圧倒的に伸びたと感じますまた自由時間が多く(自分のやりたいことに取り組める時間)資格取得などにも取り組むことができました。
2年生からは1年生の時と同じような感じなのでこの制度にあき、N高でできる様々な課外活動系を重点的に取り組みましたそのおかげで日本、世界など様々なことが知れました(課外活動は全国各地、海外の課外活動もあります)。また短期で語学留学に行き様々な成長をすることができました。また予備校にも通い始め学力も伸びすごく充実していました(ちなみに2年生は週3です)
3年生では受験のため課外活動とかは一切せずに勉強に集中しました私はn高の場合いかに自立できるかで、評価が1~5は変動してくると感じます理由は宿題がなかったり、学校の中で自習の時間が1日の半分を占めるからです。
その時間を自分のためになる時間として使うかはたまたYouTube見てしまうか生徒の判断ですが自習の時間を活かせるかでN高を検討した方が私は良いと感じました自分のやりたいことをすでに持っている人にとってN高はお勧めできる価値のある学校だと感じます
良かった点私は人間関係の悩みでN高等学校に変えたので、まず人付き合いを強制されないというところにとても安心感を感じられ良かったです。
次にN高等学校のネットコースはとても登校日数が少ないので往復3時間かけていた登校時間の短縮が出来たことや、どんな時間でも好きなだけ授業動画を見ることが出来る機能があり、自分の集中出来るタイミングや自分のその時にできる量をやる事が出来たため、自由な時間がとても増えました。
その時間を使い、自分のスキルアップの時間を多く取る事が出来たのは今でもとてもよかったと感じています。
悪かった点ネットコースなので先生や他の生徒達との繋がりが弱いです。The高校生のような青春を送るのは少し難易度が高いと感じます。一応N高等学校には部活のようなチャットグループがあるのですが、キャンパスで面識があるお友達同士しか喋っていないことが多いので、ネットコースの人は上手くいかないこともあるかもしれません。
学校について私が言ったらキャンパスの建物はとても綺麗で、机等も使いやすい形でした。自動販売機等もあり不便さを感じることは無かったです。コロナ対策もしっかりしていて安心して登校する事が可能です。
結論から申し上げると、この高校に通うことができて本当に良かったと思います。学習面に関しては、自己管理能力や自己学習能力が求められますが、その点に関しては他の通信制高校でも大差はないと思います。
N高等学校の一番素晴らしかった点は、プログラムやイベントの多さです。投資部や起業部などの他の学校にはないユニークな部活があったり、ニコニコ動画を活用した大久保な文化祭が執り行われたりするなど、この高校でしかできない体験をたくさんすることができました。また、進路サポートも充実していて、国内の大学や専門学校進学に関する指導だけではなく、海外大学への出願サポートもあるため、さまざまな進路希望に対応してくれます。先生方は比較的若く、穏やかな方々が多い印象です。
中には学生時代不登校だった先生もいらっしゃるので、学校に生きづらいという生徒に寄り添ってくれる先生もいらっしゃいます。費用に関しては、週五日の通学コースだと本当に高いです。おそらく、全日制の私立高校よりも高いと思います。学費を節約したい場合は、ネットコースにして、オンライン上でさまざまな部活やイベントに参加するのがいいのではないかと思います。
よかった点は全日制の高校いってた時よりかは時間に縛られずノーストレスで家で学習していたところや、他の高校生と違い時間がありふれていたので、すきな趣味に没頭したり、今まで習ってきてなかったスキルを習得する時間を作れたことがよかったところです。
悪かった点は、全日制とは違い自宅にいる時間が多く、それと授業も先生方から渡された動画や課題をこなすだけだったので人とのコミュニケーションのできる場がなくて友達を作ろうにも作れない状況でした、ですが年に三回は指定された場所で授業をうけるのがあり、同じ気持ちをもってる優しい方もいれば、口が悪い子もいたりで微妙でした。
学校の先生の雰囲気は、誰よりも優しく、誰よりも相談に乗れる方々がいて疲れた心を癒してくれる場所でもありました。全日制の高校の先生なんか大抵が心がないやつしかいないので通信は優しい方がいっぱいいました。最後に迷ってる子がいるとしたら、通信も悪くない場所です!
 編集長 阪口
編集長 阪口
・学費が安い(年間10万円程度)
・生徒数日本No.1(=生徒が最も選んでいる通信制高校)
・東大・国立難関私大の合格実績多数
と学費の安さ、実績、学びやすさは日本トップ。通信制高校進学を考えたら、最初に検討したい学校です。
N高等学校の資料を取り寄せる>>

| 学費 | 一人ひとりに合わせて最適な料金プランを作成。
詳細は公式サイトでお問い合わせください。 |
| 開講コース | 【普通科】高校卒業を目指すコース
【特進科】大学進学を目指すコース |
| 入学時期 | 新入学:4月 10月 / 編入転入:随時 |
| 専門授業 | 特進科(大学進学コース) |
| 本校所在地 | 東京都千代田区飯田橋 1-10-3 |
| キャンパス | 全国に120キャンパス以上 |
評価的には4かなと思います。でもそこまで悪いところがあるわけでもないのですが、普通の高校の方がいい気がします。
良かった点は、ネットコースなのであまり人と会わないことです。正直人とのコミュニケーションなどは得意ではない方だったのでその方がありがたかったです。なので周りを気にせずに自分自身で勉強に取り組むことができたのでよかったです。
悪かった点としては、これをいうのもあれなんですが人とのコミュニケーションが取れないこと、そうなることで今後の社会に出た時などに人とのコミュニケーションは必ずと言って必要なものなので困りました。なので今でもネットを使ったような仕事をしていて人とあまり関わらないような仕事をしているので結果よかったか悪かったかわかりません。
今後このような通信制の学校などを考えているのであれば私なりには正直、普通の高校に通っていろんな人とコミュニケーションを取ることが大事になってくるのかなと思いました
まず、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、通信制教育に特化した学校です。自分のペースで学習が進められるため、仕事やアルバイト、病気や怪我などで通学が難しい場合でも、学業を続けることができます。また、進路に合わせてカリキュラムが選べるため、自分の目標に向かって無理なく学ぶことができます。
次に、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、豊富な教材や学習支援が用意されています。学習教材は、オンラインで提供されるため、自宅や外出先など、好きな場所で学習ができます。また、学習相談や質問に対する返信など、サポート体制も充実しており、生徒が不安なく学習を進めることができます。
さらに、トライ式高等学院 仙台キャンパスは、先進的な取り組みが特徴です。例えば、AIを活用した学習支援システムが導入されており、生徒の学習状況を分析し、適切なアドバイスを出すことで、効率的な学習を促進しています。また、単位制度を採用しているため、必要な単位を取得することができれば、自由に卒業時期を選択できるなど、柔軟な学習スタイルをサポートしています。
最後に地域に根ざした学校として、地域との交流やボランティア活動に力を入れていることも魅力的です。例えば、地域の祭りやイベントに参加したり、老人ホームや児童福祉施設などでボランティア活動を行ったりすることで、社会貢献の意識を育てることができます。
トライ式高等学院の東京キャンパスは生徒数も多く、部活動や修学旅行、留学制度もあり、全日制高校と変わらない学校生活を送ることができました。大学受験に特化した特進科は先生が受験などのプランを立ててくださり、分からないところは丁寧に教えてくれます。全日制高校にはない、復習する授業もあり無事に第一志望の国公立大学に進むことができました。
欠点としては学費がとても高いことです。提携通信制高校の学費に加えてサポート費用がかかるため、年間学費は100-120万円ほどでした。一般の全日制高校+予備校にかかる費用と考えると相応かなとは思いますが、入学を希望する方は学費の把握はしておくようにしましょう。
僕は高校2年生ときに、私立の全日制高校から転入しました。その際不登校だったため、1年生の取得単位数は0でした。ですが、留年をしたくなかった僕は、留年せずに大学に進学できる学校を探している際にこの高校を見つけました。学力テストはいつもギリギリだった上、授業もろくに行っていませんでしたが、トライ式高等学院はそんな僕でもマンツーマンで指導をしてくれ、無事に三年間で卒業することができました。この学校を選ばなければ大学には進学できなかったでしょう。
| 募集定員 | キャンパスにより異なる |
| 偏差値 | なし(詳細) |
| 出願期間 | 公式サイトにてご確認ください |
| 選抜方法 | 面接+作文(一般入試のみ) |
| 進路内訳 | 卒業率:99.5%
*2022年3月卒業生の実績
大学進学率:69.7%
※大学進学率とは、進路決定者のうちの大学・短大・専門職大学に合格した者において。卒業/大学進学率2024年自社調べ。出典:文部科学省「学校基本調査」在籍生徒数3500人以上の通信制高校・サポート校において進学率全国1位。2023/3/23 産経メディックス調べ。令和4年度の学校基本調査:大学進学率23% |
| 国公立大学 | 東京大学/大阪大学/北海道大学/九州大学/神戸大学/筑波大学/金沢大学/広島大学/熊本大学/北海道教育大学/山形大学/東京学芸大学/電気通信大学/新潟大学/信州大学/静岡大学/福井大学/京都教育大学/京都工芸繊維大学/山口大学/愛媛大学/高知大学/長崎大学/鹿児島大学/琉球大学/前橋工科大学/東京都立大学/横浜市立大学/諏訪東京理科大学/愛知県立大学/神戸市外国語大学/兵庫県立大学/広島市立大学/北九州市立大学/熊本県立大学 ※2024年度大学入試の実績 |
| 私立大学 | 早稲田大学/慶應義塾大学/上智大学/東京理科大学/学習院大学/明治大学/青山学院大学/立教大学/中央大学/法政大学/関西学院大学/関西大学/同志社大学/立命館大学/日本大学/東洋大学/駒澤大学/専修大学/成城大学/成蹊大学/津田塾大学/南山大学/京都産業大学/近畿大学/甲南大学/龍谷大学/西南学院大学 ※2024年度大学入試の実績 |
 編集長 阪口
編集長 阪口
マンツーマンで指導が基本で、どんな状況の生徒でも柔軟に対応してもらえます。不登校や発達障害を持つ生徒、大学進学を考えている生徒に特におすすめです。
トライ式高等学院の資料を取り寄せる>>
 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生



 編集長 阪口
編集長 阪口
 編集長 阪口
編集長 阪口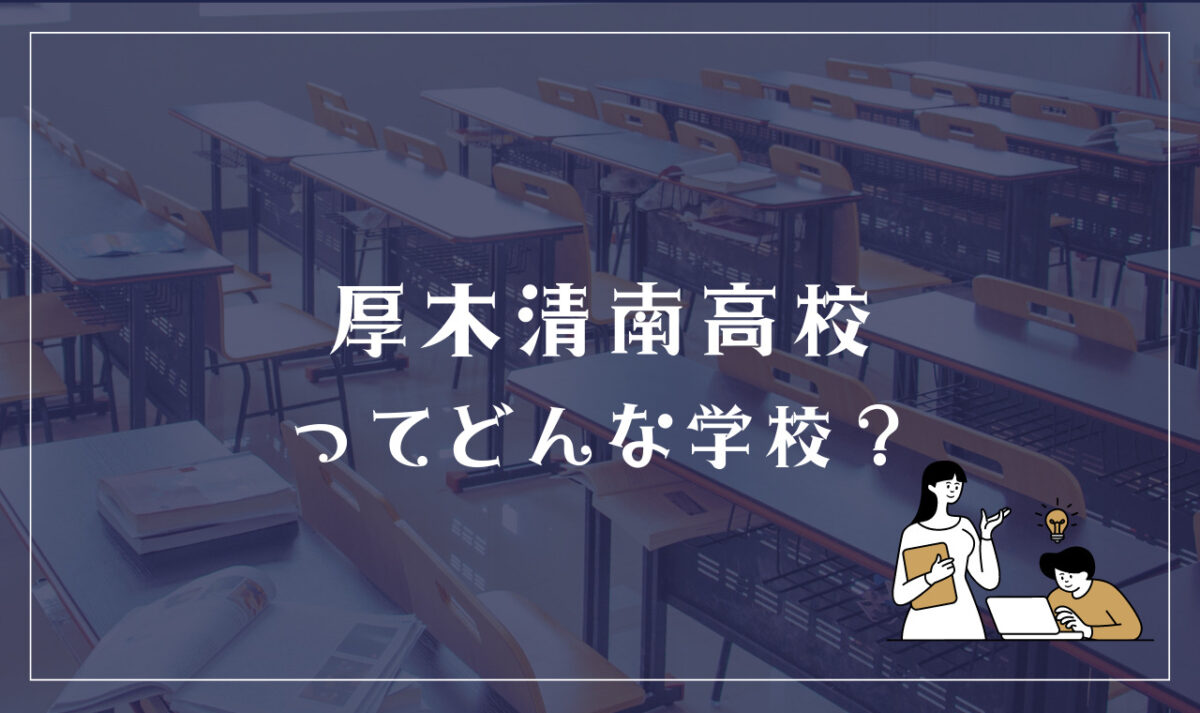
 卒業生
卒業生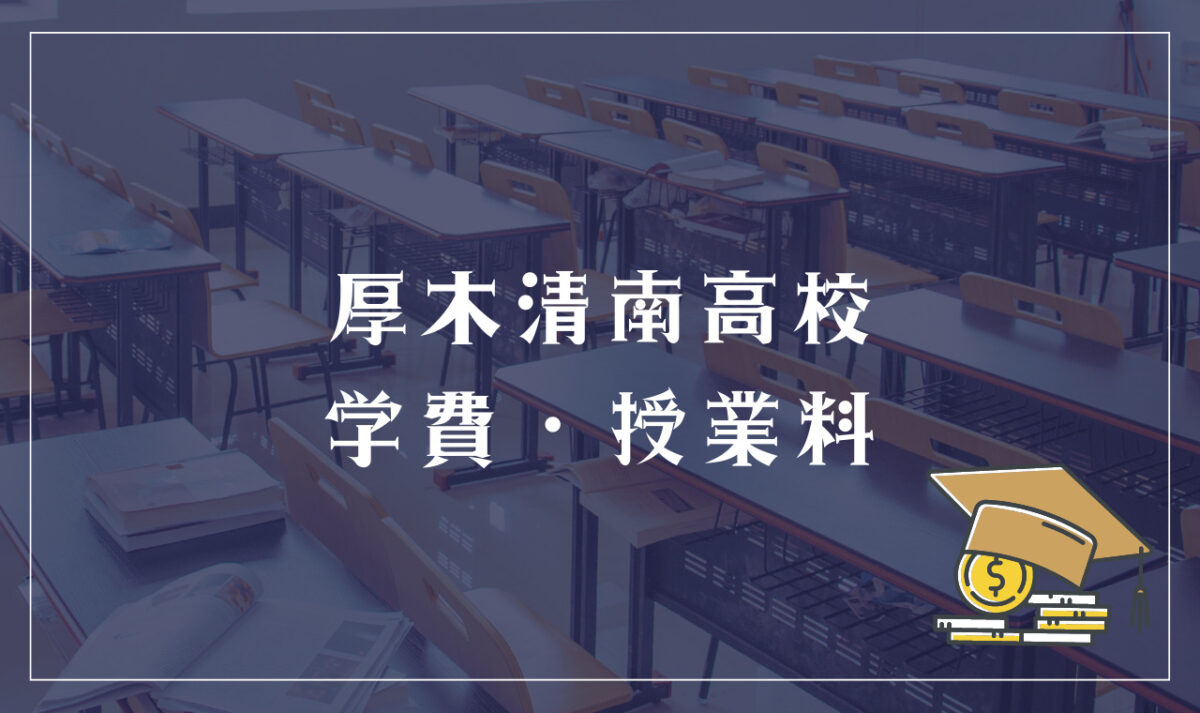
 卒業生
卒業生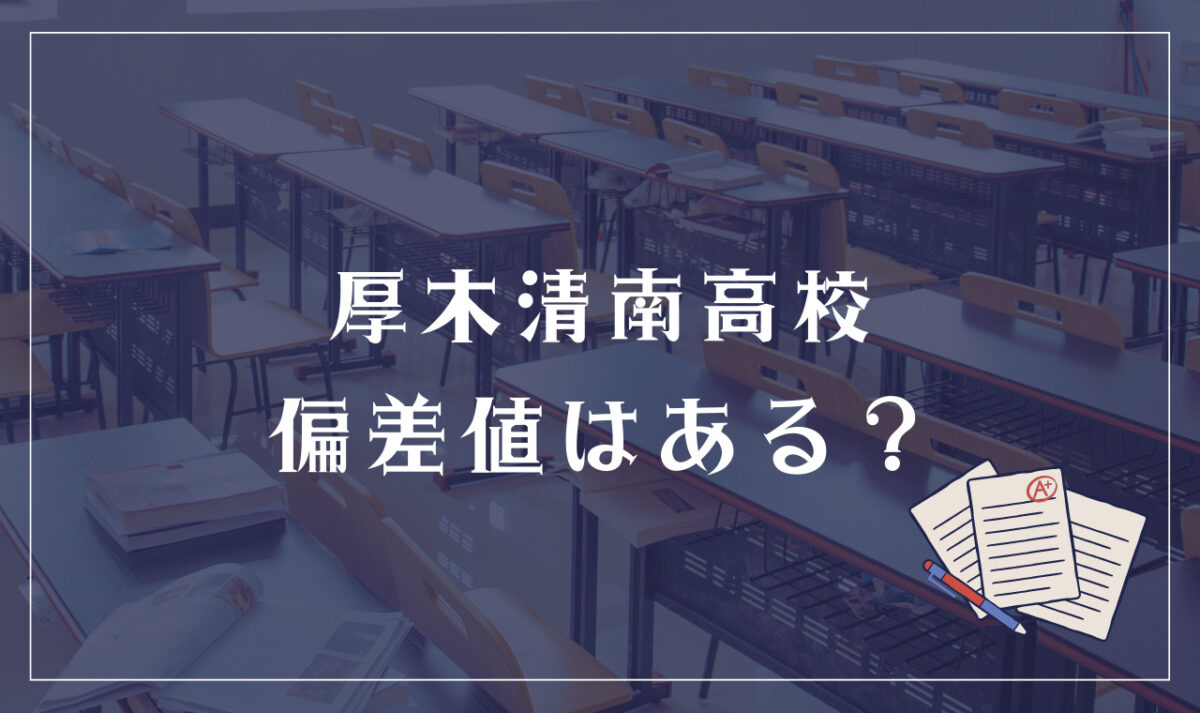
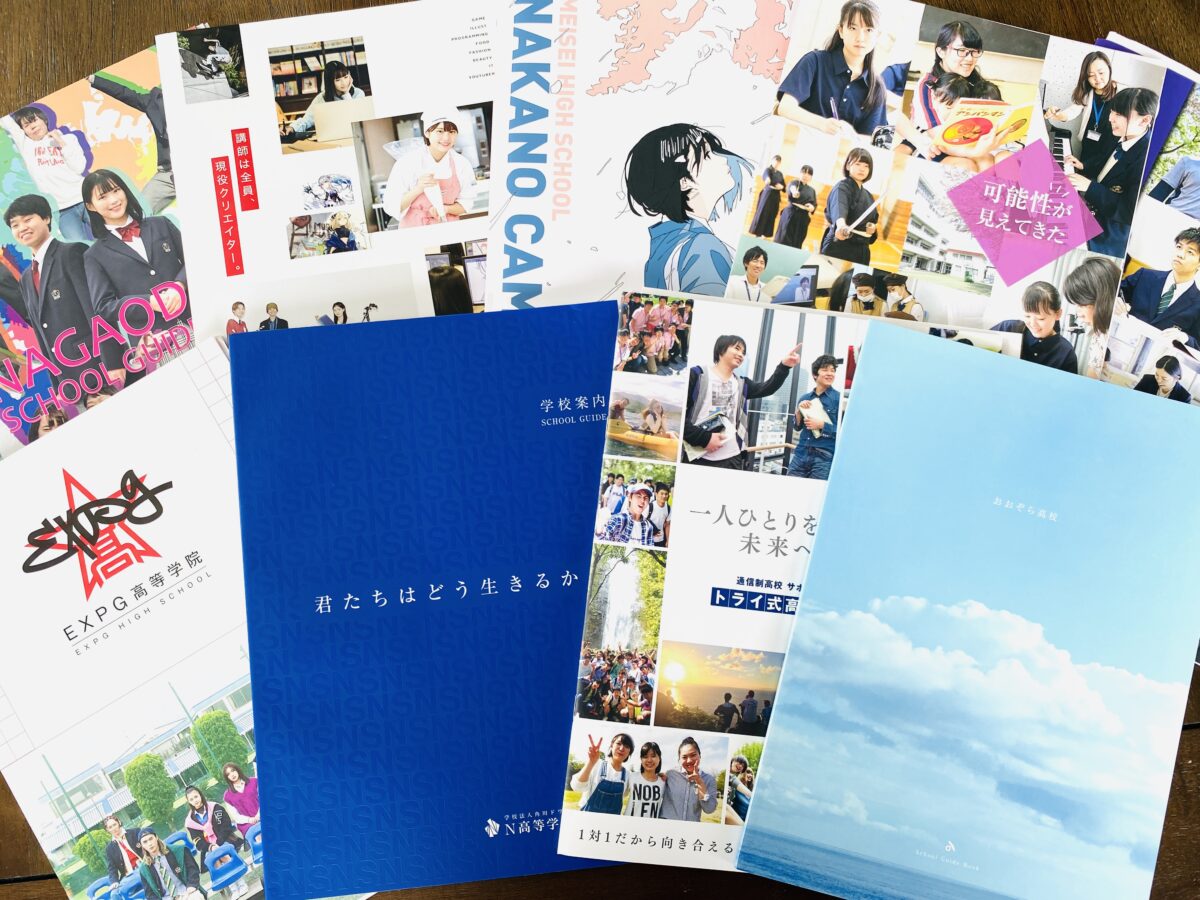

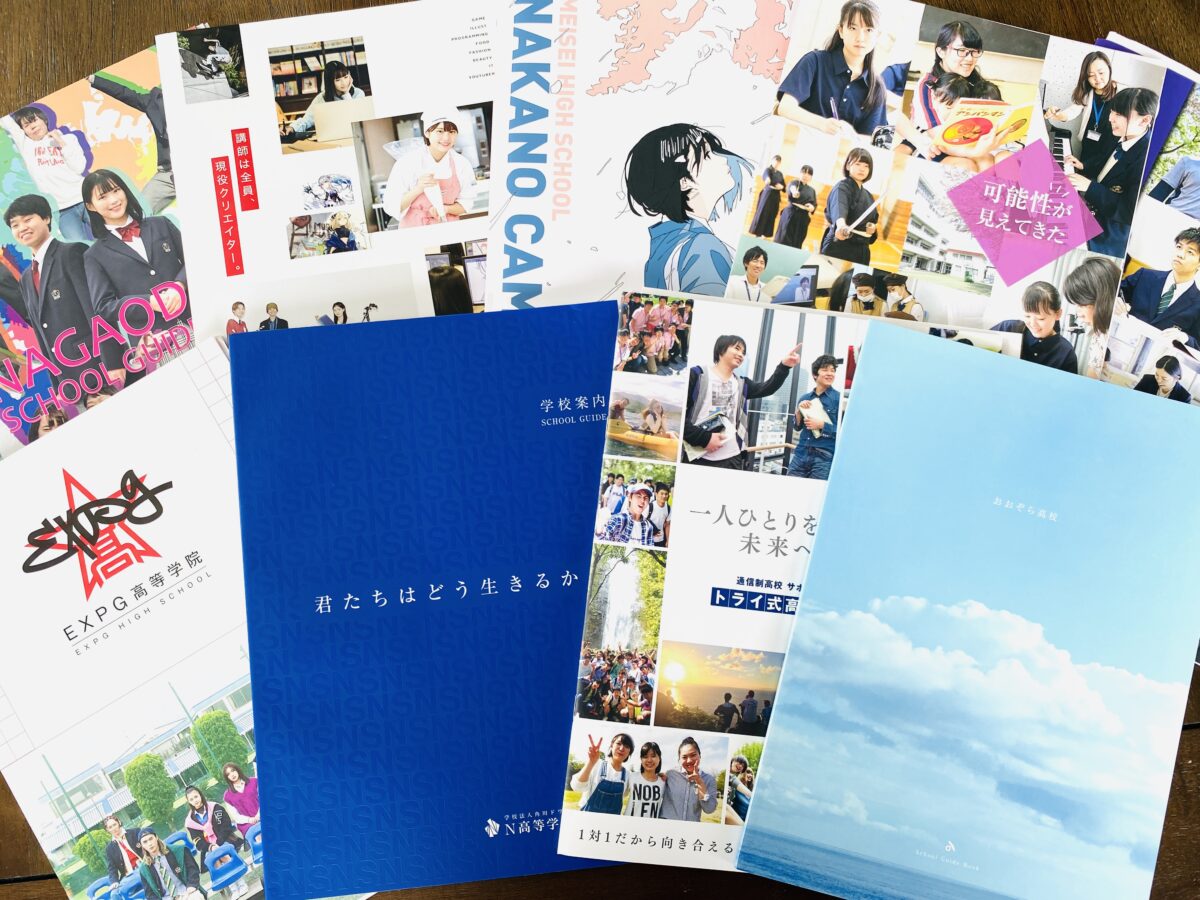

 卒業生
卒業生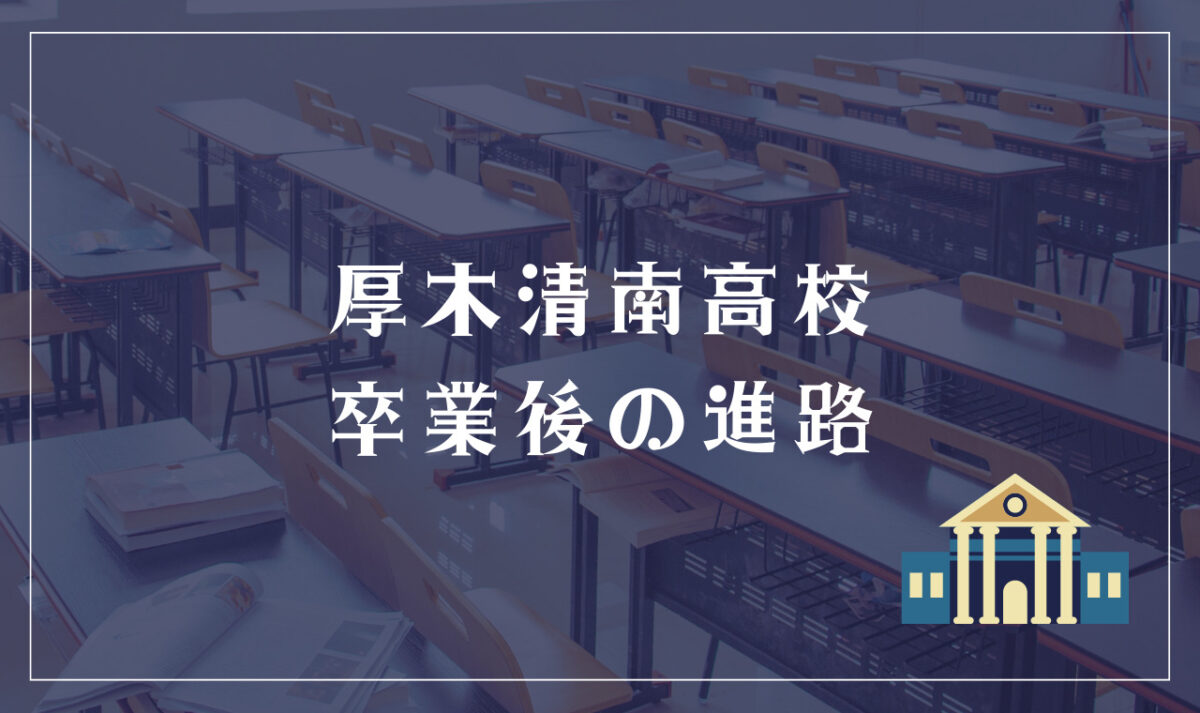
 卒業生
卒業生 卒業生
卒業生



 編集長 阪口
編集長 阪口
 編集長 阪口
編集長 阪口